【管理栄養士が解説】高齢者の低栄養とは?原因・症状・予防などについて解説

「高齢者の低栄養について知りたいな」
「高齢者の低栄養を予防する方法はあるかな」
という方のために、高齢者の低栄養についてまとめました。
高齢者が低栄養に陥ると、フレイルを引き起こしたり寝たきりのリスクが高まったりするため、適切な対応で予防することが大切です。
高齢者が低栄養になりやすい原因や症状、予防法を解説するため、参考にしてください。
高齢者がなりやすい「低栄養」とは?
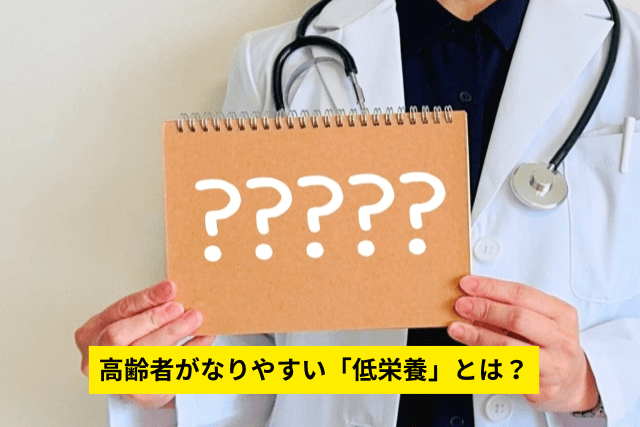
低栄養とは、エネルギーやたんぱく質、ビタミン、ミネラルなど体に必要な栄養素が慢性的に不足している状態をいいます。高齢者はさまざまな理由から食事量が減りやすく、低栄養になりやすい状態です。
毎食食べていたとしても、食べる量や内容によっては低栄養を引き起こすことがあるため、食事がとれているからといって安心はできません。
低栄養が続くと、筋力低下や免疫力低下、浮腫みやすくなるなど、高齢者の健康に深刻な影響を及ぼします。転倒や骨折を起こすと、寝たきりのリスクが高まってしまうでしょう。
高齢者本人の自覚なく進行するケースが多いため、家族など周囲の人間が早めに気付いて予防することが大切です。特に注意すべき症状や原因について把握し、早い段階で対処できるようにしましょう。
食べているのに高齢者が低栄養になる原因について詳しくはこちら↓
食べているのに高齢者が低栄養になる原因や対策、アルブミンを上げる食事など紹介
特に注意すべき症状
- 体重減少
- 筋力低下
- 免疫力低下
- 浮腫み
上記のような症状がみられた場合は低栄養を起こしている可能性があり、注意が必要です。必要な栄養素が不足すると筋肉量が減少し、体重減少や筋力低下につながってしまうでしょう。
また、低栄養が続くと免疫を司る細胞にも十分な栄養が行き渡らず、免疫力が低下します。風邪などの感染症にかかりやすくなるでしょう。
高齢者が一度体調を崩すと、完全に回復するまでに時間がかかります。症状が長引けば、活動量が減って筋肉量が低下し、フレイル状態になるおそれも出てくるでしょう。
低栄養によって血液中のアルブミン値が基準値より低下すると、浮腫みを引き起こしやすくなるため、浮腫みが見られる場合も注意しなければなりません。
フレイルについて詳しくはこちら↓
フレイルとは?症状や原因から予防方法までわかりやすく解説!サルコペニアとの違いも
原因
- 消化機能の低下
- 運動量の低下
- 何らかの疾患
- 社会からの孤立
高齢者が低栄養になりやすい原因として、上記の項目が挙げられます。
加齢に伴って胃の粘膜は萎縮するため胃酸の分泌量が減少し、小腸や大腸も消化液を分泌する機能や栄養素を吸収する機能が低下します。消化機能が低下すると体が必要とする栄養素を十分に摂取することができず、低栄養につながってしまうでしょう。
また、加齢による筋肉量の低下によって外出の頻度が減ると、運動量が低下します。運動量が低下すると食欲がわかないため、食事量が減って低栄養を招く原因になるでしょう。
何らかの疾患や服薬の影響で食事摂取量が低下し、低栄養を引き起こすこともあります。胃や腸などの消化器疾患やうつ病、がんなどは、食事摂取量の低下を引き起こす可能性が高い疾患です。服薬している場合は、薬の影響で食欲不振や消化機能低下を招いているケースもあります。
社会からの孤立など環境面の悪化も低栄養になり得る原因のひとつです。高齢になると、退職したり独居になったりして家族や地域、社会とのつながりがなくなる人は少なくありません。
社会からの孤立感を抱くと食事に対する意欲が失われ、食事量が減ったり栄養バランスが偏った食事で済ませるようになったりし、低栄養を招くリスクが高まります。
高齢者の体重減少について詳しくはこちら↓
高齢者が体重減少する原因は?対策と注意点などを紹介
高齢者の低栄養を予防する方法

- たんぱく質を意識した食事
- 1日3食食べる※必要であれば間食を取り入れる
- 米・パン・麺などの主食を毎食摂る
- 定期的な運動
高齢者の健康や生活に大きな影響を及ぼす低栄養は、上記のように日常生活を整えることで対策が可能です。低栄養を予防する方法を4つ、ご紹介します。
たんぱく質を意識した食事
低栄養予防には、体に不可欠な栄養素であるたんぱく質を意識した食事を心がけましょう。たんぱく質は細胞や筋肉をつくる材料であり、筋肉量の維持や免疫機能の維持に不可欠です。十分なたんぱく質摂取は、フレイル予防にもつながります。
良質なたんぱく質は、鶏肉や牛肉などの肉類や牛乳やヨーグルトなどの乳類、鮭やアサリなどの魚介類、豆乳や蒸し大豆などの大豆製品に多く含まれているため、意識して食事に取り入れましょう。
できるだけ毎食、たんぱく質を含む食品を取り入れるのがポイントです。豆乳やチーズ、ギリシャヨーグルト、プロテインバーのように、忙しいときでも手軽に取り入れられるたんぱく質食品を活用すれば、毎食たんぱく質を摂取することができるでしょう。
低栄養を予防する食事レシピはこちら↓
【管理栄養士監修】高齢者の低栄養を予防するための食事レシピ
1日3食食べる※必要であれば間食を取り入れる
高齢者の低栄養を防ぐには、1日3食食事をすることが重要です。加齢により食欲や食事量が低下しやすい高齢者は、食事の回数が減るとエネルギーやたんぱく質などの摂取量が不足しやすくなります。知らず知らずのうちに低栄養に陥っているケースも少なくありません。
1回あたりの食事量が少なくても、回数を確保することで1日トータルの食事摂取量を維持できるでしょう。
また、1日3回の食事に加えて間食を取り入れるのも一つの方法です。カステラやプリン、どら焼き、蒸しパンなどはエネルギーとたんぱく質を摂取しやすいため、間食に適しています。
米・パン・麺などの主食を毎食摂る
米やパン・麺などの炭水化物は主要なエネルギー源となる栄養素であるため、適切な量を食べると体が必要とするエネルギーを摂取できるでしょう。
日本人は、エネルギーの約60%を炭水化物から摂取しています。そのため、毎食のメニューに米やパン、麺といった主食を取り入れてしっかりエネルギーを摂りましょう。
焼き芋やシリアルも炭水化物が多く含まれており、手軽に使える食品です。忙しいときに活用してみましょう。
高齢者のカロリー不足について詳しくはこちら↓
【管理栄養士監修】高齢者のカロリー不足を補う方法
定期的な運動
運動すると活動量が増えるため、普段よりも食欲がわいて食事量が増える可能性があります。定期的な運動は生活リズムを整え、規則正しい食事習慣や食事量の維持にもつながるでしょう。
ウォーキングやラジオ体操、ヨガなど、無理なく続けられる運動を継続して取り組むことがポイントです。
高齢者が自宅でできる運動について詳しくはこちら↓
理学療法士考案!高齢者が自宅でできる運動を動画で紹介
低栄養防止の目安となる高齢者のBMI
| 年齢(歳) | 目標とするBMI(kg/㎡) |
|---|---|
| 18~49 | 18.5~24.9 |
| 50~64 | 20.0~24.9 |
| 65~74 | 21.5~24.9 |
| 75以上 | 21.5~24.9 |
引用:健康日本21アクション支援システム~健康づくりサポートネット~│厚生労働省
上記の表は、低栄養予防の目安となる高齢者のBMIを、総死亡率を低く抑える観点からまとめたものです。高齢者では、ほかの年齢層に比べると目標とするBMIの数値が高く設定されています。高齢者において、いかに食生活を整えて体重を維持することが大切なのかが分かるでしょう。
ただし、上記はあくまで目安の数値であるため、高齢者個人の生活や健康状態に合わせて対策をとる必要があります。
※定期的にBMIを計算して痩せすぎていないか確認しましょう。
日々のちょっとした工夫で高齢者の低栄養を防ごう
低栄養はエネルギーやたんぱく質、ビタミン、ミネラルなど体に必要な栄養素が慢性的に不足している状態です。高齢者は身体的・精神的な理由から食事量が低下しやすく、低栄養に陥りやすいため、日ごろから注意しなければなりません。
体重減少や筋力低下、浮腫みなどの症状は、特に気を付けましょう。
低栄養の予防は、1日3食食事をする、たんぱく質・エネルギーを摂取する、定期的に運動することがポイントです。日常生活の中でできる小さな工夫の積み重ねで、高齢者の低栄養を防ぎ、高齢期を健やかに過ごすための基盤を整えましょう。_1.jpg)
PROFILE

管理栄養士
今井尚美
(Imai Naomi)
カテゴリー|ブログ





 高齢者
高齢者
 高齢者
高齢者
 高齢者
高齢者
 高齢者
高齢者