要介護認定を受けるには?するべきことや入院中の申請方法・メリットデメリットなど
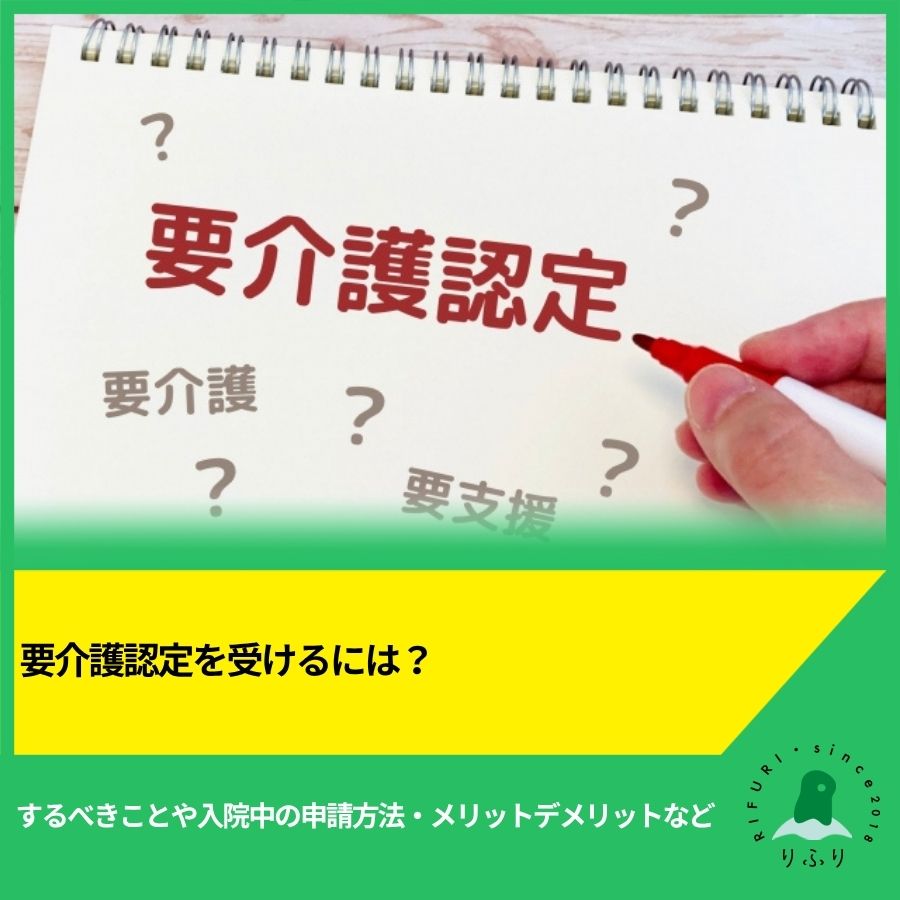
「要介護認定を受けるには何をすればよい?」
「要介護認定は入院中でも申請できる?」
など要介護認定を受けるための手順について知りたい方のために、要介護認定を受けるにはどうすればよいかをまとめました。
申請前の準備や入院中の申請方法、認定結果に納得がいかない場合の対処法についても解説します。
要介護認定について

要介護認定とは、介護保険制度においてどの程度の介護が必要かを判定するしくみです。
市区町村が実施する認定調査と主治医意見書をもとに、介護の必要度を「要支援1・2」「要介護1~5」の7段階で判定します。
要介護認定を受けると訪問介護やデイサービス、特別養護老人ホームへの入所など、さまざまな介護保険サービスを自己負担1~3割で利用できます。
要介護認定について詳しくはこちら↓
要介護認定とは?区分や判定基準・申請から要介護度決定までの流れなどを解説
要介護認定の申請方法

- 必要書類を揃えて市区町村の役所に提出
- 訪問調査・主治医の意見書
- 一次判定(コンピューター判定)
- 二次判定(介護認定審査会)
- 認定結果通知書と介護保険被保険者証交付
介護保険の申請は、まず必要書類を揃えて市区町村の役所に提出することから始まります。提出書類には、申請書のほか、本人確認書類や医療機関からの情報などが必要です。
申請が受理されると、市区町村の担当者が申請者の自宅などを訪問して、日常生活の様子や身体状況を確認する訪問調査が行われ、あわせて主治医からの意見書も提出されます。
訪問調査や主治医の意見書をもとに行われる一次判定は、調査結果を点数化して要支援・要介護の見込み度をコンピューターで算出したものです。
一次判定の後、介護保険審査会による二次判定が行われます。一次判定の結果や個別の事情を踏まえて最終的な認定が決まるでしょう。
認定結果は「認定結果通知書」として申請者に送付されます。
要介護認定の流れについて詳しくはこちら↓
要介護認定を受けて介護保険サービスを利用するまでの流れやその他必要な手続きなど
要介護認定を受けるためにするべき手続き上の準備

- かかりつけ医を決める
- 誰が手続きするか決める
- 申請に必要な書類の準備
要介護認定の申請前に、上記を整えて準備しておきましょう。
かかりつけ医を決める
要介護認定では主治医が心身の状況を説明する主治医意見書が必要であるため、かかりつけ医を決めておきます。
普段から診察し、持病や体調について把握しているかかりつけ医であれば、継続的な診療や経過観察の情報を踏まえたより正確な意見書を作成してもらえるでしょう。
かかりつけ医を決めておけば認定調査と並行して意見書作成も進められるため、準備期間の短縮にもつながります。
誰が手続きするか決める
要介護認定の申請は基本的に本人が行いますが、体調などの理由で難しい場合は「家族」や「親族」が代理で申請可能です。
本人も家族も難しい場合は「地域包括支援センター」「居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)」「介護保険施設」などに代行を依頼できます。
代理人が申請する場合は委任状など追加で必要な書類があったり、要介護認定申請書に代理人の情報を記入したりするため、誰が申請するか事前に決めておくといいでしょう。
本人以外で要介護認定の申請が可能な人についてはこちら↓
要介護認定を申請できる人はこんな人!条件や必要なものなど解説。本人以外の申請は?
申請に必要な書類の準備
- 要介護認定(要支援認定)申請書
- 介護保険被保険者証(65歳以上の方)
- 健康保険被保険者証(40~64歳の方で特定疾病による申請の場合)
- 本人確認書類(運転免許証など)
- マイナンバー(個人番号)が確認できる書類
- 委任状(本人以外が申請を代行する場合)
要介護認定の申請には、上記の書類が必要です。
「要介護認定(要支援認定)申請書」は市区町村の介護保険担当窓口で入手できるほか、各自治体の公式サイトからダウンロードも可能です。
必要書類は自治体によって異なる場合があるため、申請前にお住まいの市区町村に確認しましょう。
要介護認定を受けるためにするべき情報整理

- 現在の生活状況や問題点の整理
- 認定調査質問項目の確認
- 認定調査日の調整
要介護認定を申請する際は、上記の情報を整理しておきましょう。特に現在の生活状況や問題点は要介護認定の結果を左右するものであるため、しっかりまとめておくと安心です。
現在の生活状況や問題点の整理
日常生活で支援が必要な状況や困っていることを整理し、具体的な内容を伝えられるようにしましょう。
最近見られる要介護者の変化や、家族が実施している支援、困っていることなどをメモすると整理しやすくなります。
客観的な記録が重要であるため、普段介護者が無意識に行っている支援も把握することが重要です。
手助けがないとできないことを明確にすると、調査員にも情報が伝わりやすいでしょう。
認定調査質問項目の確認
認定調査では、全国共通の調査票に基づいて約70項目以上の質問が行われます。
調査項目の内容をあらかじめ確認して質問に備えると、調査の際に話しやすくスムーズに進行できるでしょう。
質問内容は大きく分けて、身体機能・起居動作、生活機能、認知機能、精神・行動障害、社会生活への適応などの分野に分かれています。
厚生労働省の公式サイトでも、認定調査票の確認が可能です。
認定調査日の調整
要介護認定の認定調査は、あらかじめ本人や家族などの介護者と日時を調整したうえで行われます。
本人の状態をよく知っている家族や介護者が必ず同席できる日時を設定しましょう。
本人だけでは伝えきれない日常生活の困りごとや介護の実態を、調査員に家族が補足して説明する必要があります。
調査は約1時間程度かかるため、その時間を確保できる日を選ぶとスムーズです。
要介護認定で決まる要介護度一覧
| 自立(非該当) | 介護や支援を受けなくても生活できる |
|---|---|
| 要支援1 | 基本的には自立して生活できるが、一部の家事などで助けが必要 |
| 要支援2 | 一人での生活は可能だが、要支援1よりも援助を必要とする範囲が広い |
| 要介護1 | 生活の多くは自力でできるが、身体機能や判断力の衰えが見られ、部分的な介助を要する |
| 要介護2 | 食事や排泄に見守りや介助が必要 |
| 要介護3 | 立ち上がりや歩行が自力では困難になり、排泄・入浴などに全面的な介助が必要 |
| 要介護4 | 日常生活全般で介護なしでは困難 |
| 要介護5 | ほぼ寝たきりで、介助がなければ生活できない状態、意思疎通が難しい場合も |
上記は、要介護度別の状態を表した表です。
非該当は、日常生活において介護や支援が全く必要ないかほとんど介護の手間がかからない状態で、介護保険サービスの対象外となります。
要支援1から要介護5は、なんらかの介護保険サービスが必要であると客観的に判断された状態です。
要介護認定の結果に納得がいかない場合にできること

- 不服申し立て
- 区分変更の申請
要介護認定の結果が実際の状態より軽く判定されたと感じる場合や、必要なサービスを受けられないと判断した場合にできることは2つあります。
不服申し立て
要介護認定の結果に納得できない場合は、都道府県に設置されている「介護保険審査会」へ不服申し立て(審査請求)が可能です。
不服申し立ては、市区町村が行った要介護認定が適切であるかを第三者機関である介護保険審査会が確認・検証するものです。
審査の結果、介護保険審査会が「処分に不当な点がある」と判断した場合は、該当する認定を取り消し市区町村に再度の要介護認定を指示します。
ただし、審査の対象は「手続きや判断基準が適正に運用されたかどうか」であり、要介護度の変更が直接できるわけではありません。
要介護認定の不服申し立てについてはこちら↓
要介護認定の結果に対して不服申し立てはどこにする?メリットデメリットなども解説
区分変更の申請
区分変更申請とは、認定の有効期間中に心身の状態が変化した場合に要介護度の変更を求める手続きです。
不服申し立てと異なり、身体状況が変化した際いつでも申請できるというメリットがあります。
「認定調査時よりも状態が悪化した」「認定調査では本人の状態を正確に伝えられなかった」といった場合に有効です。
区分変更申請を行うと新たに認定調査が実施され、再度審査が行われます。
ただし、申請しても必ず要介護度が上がるわけではなく、変わらない場合や逆に下がる可能性もあることを理解しておきましょう。
入院中に要介護認定を受けるには?

- 病院のソーシャルワーカーに相談
- 代理人に申請してもらう
- 入院中の病院が認定調査の場所になる
- 入院している病院の医師に意見書作成を依頼
入院中であっても、退院後の在宅介護や施設入所に備えて要介護認定を受けることは可能です。
入院中の要介護申請についてはこちら↓
要介護認定を受けるベストなタイミングは?入院中の場合やとりあえず認定される際に注意点
病院のソーシャルワーカーに相談
入院中に要介護認定を受けるためには、まず入院している病院のソーシャルワーカーに相談しましょう。
入院中の介護認定申請は身体や心身の状態が安定していることが条件となるため、申請のタイミングや適切な手続き方法、退院後に必要な介護保険サービスをアドバイスしてもらえます。
地域包括支援センターや居宅介護支援事業者との連携も取ってくれるため、入院中で動けない状況でもスムーズに申請を進められるでしょう。
代理人に申請してもらう
入院中で本人が市区町村の窓口に行けない場合は、家族などの代理人による申請が可能です。
家族による申請が難しい場合は、地域包括支援センターに申請の代行を依頼しましょう。病院のソーシャルワーカーに相談すると地域包括支援センターと連携をとってもらえます。
入院中の病院が認定調査の場所になる
入院中に要介護認定を申請した場合、認定調査の場所は原則として入院している病院になります。
入院中の認定調査では、現在の入院生活での様子だけではなく、入院前の在宅での生活状況や退院後に予想される生活の困難さについても聞かれます。
そのため、本人の入院前の状態をよく知っている家族が同席すると退院後の介護生活もイメージしやすくなるでしょう。
入院している病院の医師に意見書作成を依頼
入院中の場合、主治医意見書は入院している病院の医師(主治医)が作成します。申請書の「かかりつけ医や主治医」欄に入院中の医師の情報を記入しておきましょう。
ソーシャルワーカーを通じて依頼すると、医師との橋渡しをしてくれます。
入院前からかかりつけ医がいる場合でも、現在の状態を最もよく把握しているのは入院先の医師であるため、入院先の医師に依頼がいくことになるでしょう。
事前準備でスムーズに介護保険サービスを受けよう
要介護認定を申請する前には、現在の生活状況や問題点を整理し認定調査質問項目を把握してから調査日程を調整するといった事前準備が必要です。
要介護認定の結果に納得がいかなくても、不服申し立てや区分変更の申請ができます。
事前にしっかりと準備しておくと認定調査で正確に状態を伝えられ、正しい要介護度の判定につながり適切な介護保険サービスを受けられるでしょう。
病院のソーシャルワーカーや地域包括支援センターなどの協力のもと、入院中であっても申請は可能です。
申請から認定結果が出るまでには約30日かかるため、介護が必要になる前やそのきざしが見えた時点で、早めに準備を始めましょう。
_1.jpg)
カテゴリー|ブログ





 高齢者
高齢者
 高齢者
高齢者
 高齢者
高齢者
 高齢者
高齢者