要介護認定でお金がもらえる?要介護度別の支給限度額や自己負担額などを解説
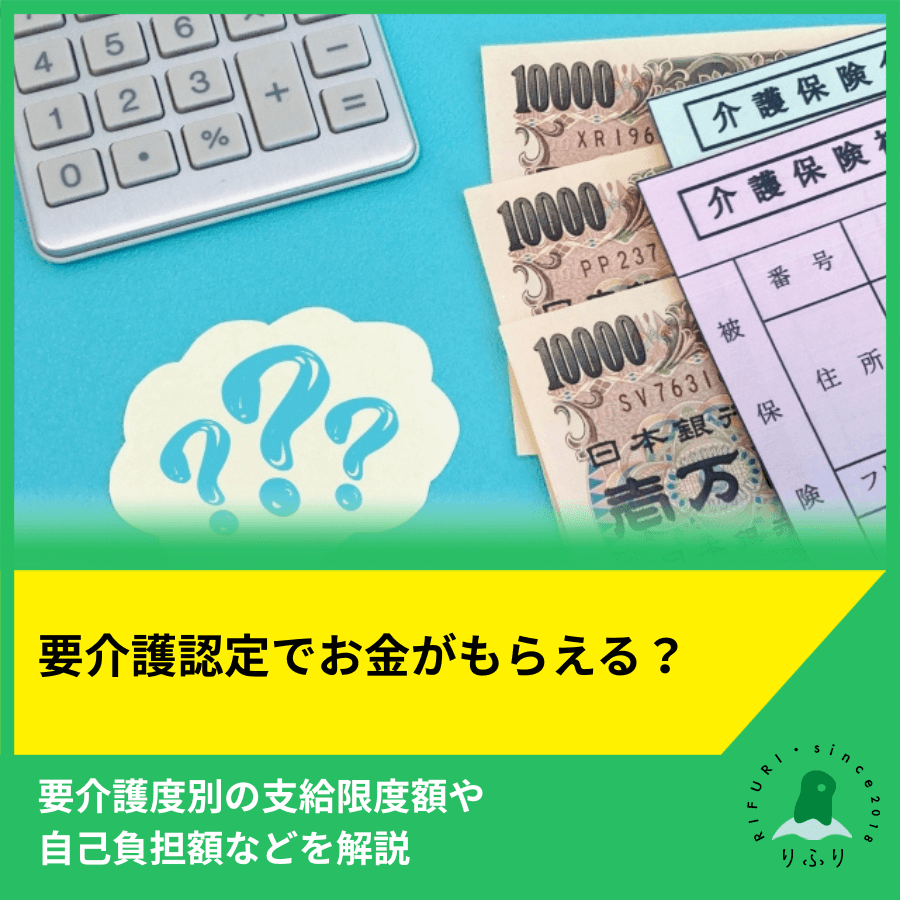
「要介護認定を受けたらお金がもらえる?」
「どれくらいの費用で介護が受けられるんだろう」
要介護認定を受けた場合、経済状況がどう変化するのか知りたい方のために情報をまとめました。要介護度別に具体的な自己負担額や自己負担額を抑える方法などを詳しく解説します。
要介護認定のしくみ
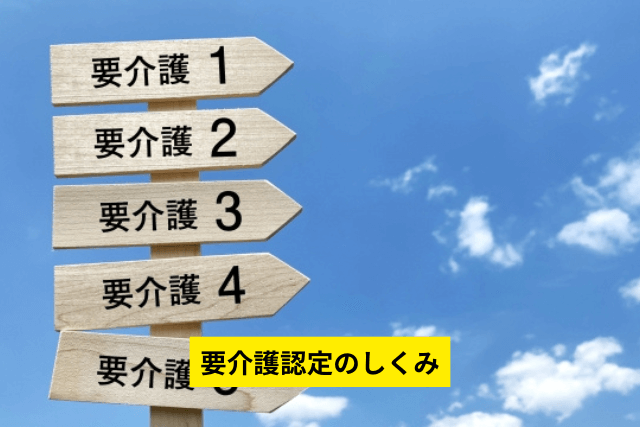
要介護認定を受けても、直接現金が給付されることはありません。
要介護認定は、介護保険サービスを受けるにあたって介護度の必要度を客観的に判定するためのものです。要介護認定を受けると、介護保険サービスが1~3割の自己負担額で利用できます。
福祉用語の購入や住宅改修などはいったん全額を支払い、あとから自己負担分を除いた額が償還払いされる形です。よって、要介護認定は介護保険を使って介護に必要なサービスの利用をサポートするためのものであり、現金給付を受けられるものではありません。
要介護認定について詳しくはこちら↓
要介護認定とは?区分や判定基準・申請から要介護度決定までの流れなどを解説
要介護度別の介護費自己負担額
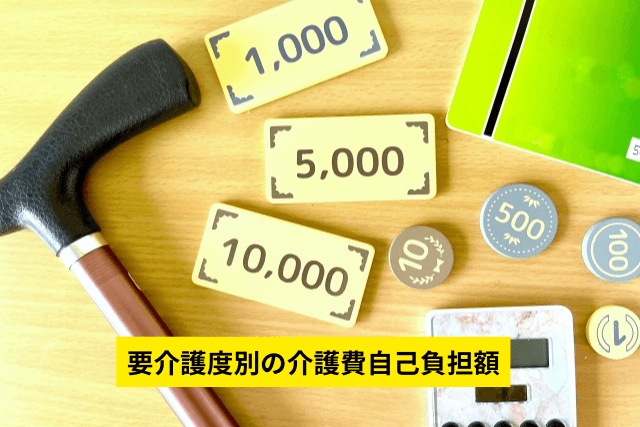
介護保険サービスの自己負担額は、要介護度や利用するサービス、所得によって異なります。
居宅サービスを受ける場合の介護度別支給限度額や施設サービスを利用した場合の必要費用目安について、分かりやすく解説します。
介護保険は使わないと損なのかについて詳しくはこちら↓
介護保険は使わないと損?要介護認定を受けたけど使わないとどうなる?
居宅サービスの要介護度別支給限度額
| 要介護度の区分 | 支給限度額 |
|---|---|
| 要支援1 | 50,320円 |
| 要支援2 | 105,310円 |
| 要介護1 | 167,650円 |
| 要介護2 | 197,050円 |
| 要介護3 | 270,480円 |
| 要介護4 | 309,380円 |
| 要介護5 | 362,170円 |
参考:厚生労働省 サービスにかかる利用料
居宅サービスを利用する際の支給限度額を要介護度別にまとめました。上記表のように、1か月あたりのサービス費は保険適用となる上限額が設定されています。限度額の範囲内であれば、介護保険サービスを自己負担1~3割で利用可能です。上限を超えた分については、全額自己負担となります。
自己負担額が大きくても「高額介護サービス費制度」や「特定入所介護サービス費」など負担を抑える制度が設けられているため、制度を利用すれば実際に支払う金額は抑えられるでしょう。
施設サービスの要介護度必要費用目安
| 施設介護サービス | 要介護1 | 19,080~57,240円 | |
|---|---|---|---|
| 要介護2 | 21,240~63,720円 | ||
| 要介護3 | 23,610~70,830円 | ||
| 要介護4 | 24,650~76,950円 | ||
| 要介護5 | 26,130~78,390円 | ||
| 居住費 | 多床室 | 27,450円 | |
| ユニット型個室 | 61,980円 | ||
| 食費 | 43,350円 | ||
| 日常生活費 | 10,000円 | ||
| 合計 | 要介護1 | 多床室 | 99,880~138,040円 |
| ユニット型個室 | 134,410~172,570円 | ||
| 要介護2 | 多床室 | 102,040~144,520円 | |
| ユニット型個室 | 136,570~179,050円 | ||
| 要介護3 | 多床室 | 104,410~151,630円 | |
| ユニット型個室 | 138,940~186,160円 | ||
| 要介護4 | 多床室 | 106,450~157,750円 | |
| ユニット型個室 | 140,980~192,280円 | ||
| 要介護5 | 多床室 | 106,930~159,190円 | |
| ユニット型個室 | 141,460~193,720円 | ||
上記は、特別養護老人ホームを1か月利用した場合の費用目安をまとめたものです。施設介護サービス費は要介護度に応じて自己負担1~3割で利用できます。居住費や食費、日常生活費は要介護度に関係なく費用が必要です。
居住費には多床室とユニット型個室があり、選択する部屋によって費用が異なります。また、施設の種類によっても費用が異なるため、あくまで目安として考えておきましょう。
介護費用の自己負担額を抑える方法

- 高額介護サービス費制度
- 特定入所介護サービス費
- 高額医療合算介護サービス費
- その他自治体の制度
介護費用の自己負担額を抑えるには、上記4つの方法があります。それぞれの制度について見ていきましょう。
高額介護サービス費制度
高額介護サービス費制度とは、介護保険サービスを利用した際の自己負担額が高額になった場合に、その負担を軽減するための公的な制度です。
居宅サービス、介護施設サービス、地域密着型サービスを利用した際、1か月間に支払った介護保険サービスの自己負担額が、所得区分に応じて求められた上限額を超えた場合に対象となります。
ただし、特定福祉用具の購入や住宅改修費用の自己負担分、施設における居住費と食費、理美容費、生活援助型配食サービスの自己負担分は支払いの対象外となるため、注意しましょう。
特定入所介護サービス費
特定入所介護サービス費とは、所得や預貯金が一定基準以下の高齢者に対して、介護施設に入所する際の居住費と食費の自己負担額を軽減する制度です。市区町村に申請して承認されると、介護保険負担限度額認定書が交付されます。
介護保険負担限度額認定書を施設に提示すれば、居住費と食費が段階的に軽減されるしくみです。対象となる施設は特別養護老人ホーム、介護老人施設、介護療養型医療施設、介護医療院で、デイケア、デイサービス、有料老人ホーム、グループホームは対象にはなりません。
対象者であっても申請しなければ介護保険負担限度額認定者は交付されません。また、介護保険負担限度額認定書には有効期間があり、期間内に更新手続きが必要になる点も知っておきましょう。
高額医療合算介護サービス費
高額医療合算サービス費は、同一世帯で医療保険と介護保険の両方を利用した際、年間の自己負担額が所得区分に応じて定められた限度額を超過した場合に超過分が払い戻される制度です。
高齢者は医療と介護の両方が必要であるケースが多く、経済的な負担が大きくなる傾向にあります。そのため、医療費と介護費の両方にかかる負担を総合的に軽減することを目的として創設されました。
高額介護サービス費の場合と同様に、特定福祉用具の購入や住宅改修費用の自己負担分、施設における居住費と食費、理美容費、生活援助型配食サービスの自己負担分は払い戻しの対象外です。
その他自治体の制度
国の介護保険制度でカバーしきれない費用や、地域ごとのニーズに対応するため、市区町村独自の助成制度が設けられている場合があります。
たとえば葛飾区には、在宅で介護を受けている高齢者に対して紙おむつを現物支給する制度があります。毎月自宅に配送されるため、日常的にかかる介護費用を抑えることができるでしょう。
医療機関などに入院中で紙おむつを利用できない場合は、紙おむつ使用料の助成が受けられます。おむつの現物支給とおむつ使用料の助成は同時に受けられません。いずれの場合も、葛飾区に申請が必要となります。
参考:葛飾区 おむつの支給・使用料の女性
要介護認定とお金に関するQ&A
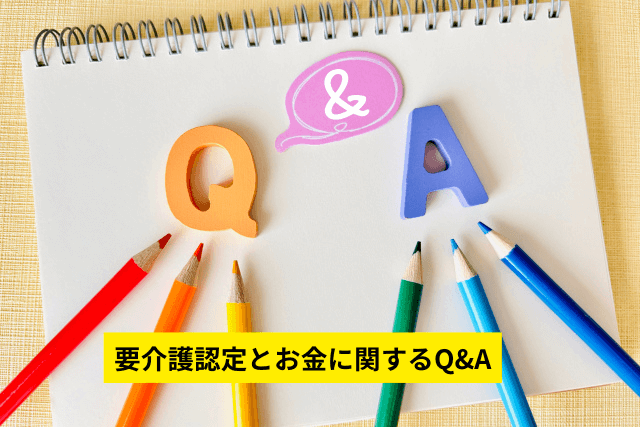
- 介護保険サービスを利用しなければお金はかかる?
- 要介護認定はいつ受けるのが得?
- 要介護認定申請中に介護保険サービスを使った場合の費用は?
上記は、要介護認定とお金に関してよくある疑問です。一つずつ、解説します。
介護保険サービスを利用しなければお金はかかる?
要介護認定を受けただけで、実際に介護保険サービスを利用しなければ、原則としてお金は一切かかりません。しかし、介護者の負担が増えたり、専門的な介護予防に取り組む機会を損失したりする可能性があります。
また、介護保険サービスではなく民間の介護サービスを利用する場合は、経済的負担が大きくなるでしょう。
とりあえず要介護認定だけ受ける場合について詳しくはこちら↓
とりあえず要介護認定だけ受けるべき?メリットデメリットや介護保険の賢い使い方
要介護認定はいつ受けるのが得?
要介護認定を受けるタイミングは、入院中の場合は退院予定日の1~2か月前、自宅生活の場合は周囲のサポートが必要だと感じる場面が増えたときがベストです。
入院中、あまりにも早い時期に要介護認定の申請をすると、身体状態が安定していないため要介護認定の調査ができない場合があります。退院の目処が立ってから申請しましょう。
自宅生活の場合、特に認知症を発症すると在宅での介護が大変になるといわれています。家族が介護疲れを起こさないように、物忘れなど認知機能の低下がみられてきたら早めに申請しましょう。
適切なタイミングで要介護認定を受けて適切な介護保険サービスを利用すると、長く元気でいられる可能性が高まります。要介護度が重くなれば介護費がかさむ傾向にあるため、介護予防に取り組んで元気でいられる期間が長いほうが経済的負担が少ないでしょう。
要介護認定を受けるタイミングについて詳しくはこちら↓
要介護認定を受けるベストなタイミングは?入院中の場合やとりあえず認定される際に注意点
要介護認定申請中に介護保険サービスを使った場合の費用は?
要介護認定の申請中は、判定される要介護度をケアマネジャーなどに予想してもらって暫定的なケアプランで介護保険サービスを利用可能です。
認定結果が「要支援1~要介護5」のいずれかになった場合、サービス利用日は申請日まで遡って保険が適用されるため、要介護度に応じて設定された1~3割の自己負担を支払う形になります。
ただし、要介護認定を申請しても非該当(自立)という結果になった場合は、利用したサービスを全額自己負担で支払う必要があるため、注意が必要です。
要介護認定は現金支給ではなく介護保険サービスの利用支援
要介護認定を受けると、介護保険サービスを1~3割の自己負担で利用できるようになります。現金が直接支給されるわけではありませんが、居宅サービスや施設サービスなどの支援を活用すれば、経済的にも体力的にも大きな助けになるでしょう。
自己負担額が大きくなった場合は、高額介護サービス費制度や特定入所介護サービス費、制度を活用すれば、実際に支払う金額は抑えられます。
介護を始める際に経済的な負担が気になるという方は、まずは要介護認定を受けることから始めましょう。
_1.jpg)
カテゴリー|ブログ





 高齢者
高齢者
 高齢者
高齢者
 高齢者
高齢者
 高齢者
高齢者