寝たきりでもできるリハビリ内容!筋力低下予防や寝たきり対策

「寝たきりでもできるリハビリはある?」
「寝たきりでもリハビリはするべき?」
寝たきりの状態になってしまった大切な方のケアに不安を感じている方のために、この記事では寝たきりでもできるリハビリ方法について解説します。
寝たきりによる体への影響や寝たきり対策についても触れているため、ぜひ参考にしてください。
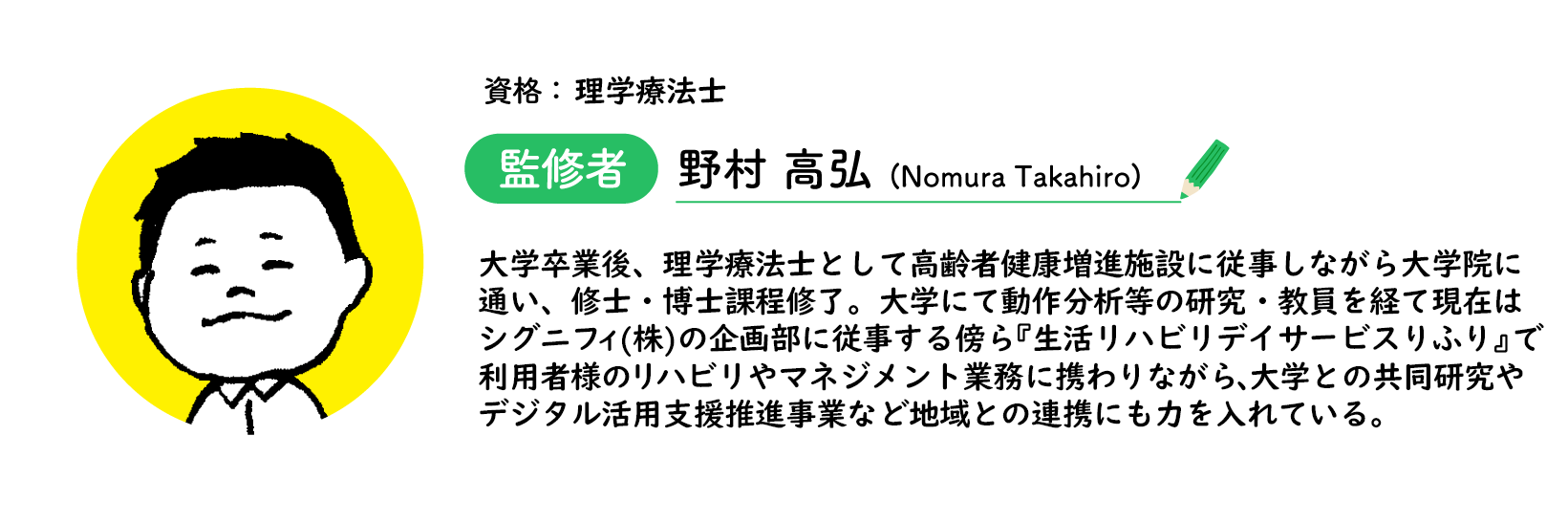
寝たきりによる弊害は筋力低下だけじゃない
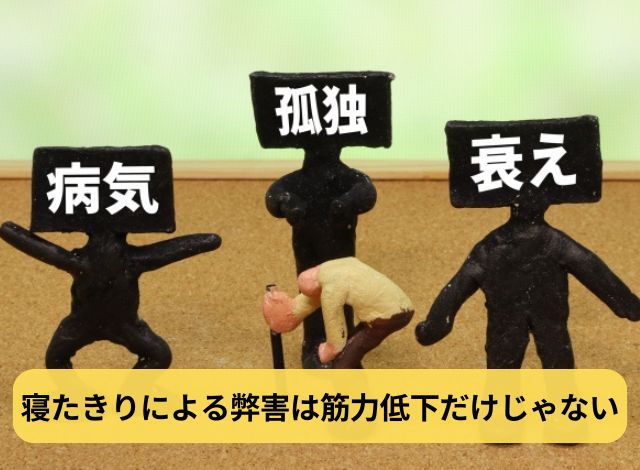
- 廃用症候群
- サルコペニア
- フレイル
寝たきり状態が続くと筋力低下の他にも、上記のような症状を引き起こす可能性があるでしょう。
特に高齢者の場合、わずか1週間の寝たきりでも、回復に1か月以上かかるともいわれています。
廃用症候群
廃用症候群とは、けがや病気によりベッドで寝たきりの生活が続いて引き起こされる、心身機能の低下です。
寝たきりによって引き起こされる体全体の機能低下が互いに関連し、さらなる機能低下が引き起こされる悪循環が特徴として見られます。
筋力が低下するとベッドから起き上がることが難しくなり、動かないことで筋力はさらに低下するでしょう。
動かない時間が長いと床ずれや便秘、食欲不振なども併発しやすくなり、新たな疾患につながる可能性が高くなってしまいます。
廃用症候群については詳しくはこちら↓
廃用症候群とは?原因や予防・回復の方法など
サルコペニア
サルコペニアは、加齢による筋肉量と筋力の低下が原因で日常生活の質が低下し、さまざまな健康リスクを高める症候群です。
70歳では男女とも20歳の筋力より30%低下し、特に下半身の衰えが進みやすいといわれています。
寝たきり状態では、さらに筋力の衰えが加速するといえるでしょう。
あっという間に立ち上がりや歩行が困難になり、さらなる活動量の減少を招きます。また、筋肉は基礎代謝にも関わっているため、内臓機能も低下します。
サルコペニアについて詳しくはこちら↓
サルコペニアとは?原因・症状・対策などについて。廃用症候群やフレイルとの違いも
フレイル
フレイルとは、高齢者の心身機能が低下し、健康な状態と要介護状態の中間に位置する虚弱な状態です。
フレイルの特徴として、身体的な面では筋力低下や疲れやすさ、社会的な面では閉じこもりがちになること、精神的な面では意欲の低下や認知機能の低下などが挙げられます。
注意すべきは、症状が相互に影響し合い、負の連鎖を生むことです。
たとえば、筋力低下により外出が減って社会との接点が減少し、意欲が低下することでさらに運動能力が衰えるといった具合です。
寝たきりは、フレイルの進行を加速させます。
フレイルについて詳しくはこちら↓
フレイルとは?症状や原因から予防方法までわかりやすく解説!サルコペニアとの違いも
寝たきりでもできるリハビリ

- マッサージ
- ストレッチ
- 筋力トレーニング
ベッド上でも実施可能なリハビリ方法をご紹介します。
介護者がサポートしながら、要介護者の状態に合わせて実施しましょう。
マッサージ
マッサージは血液循環を促進し、筋肉の緊張をほぐす効果が期待できます。
また、マッサージの際に手で触れることで、全身状態の把握も可能です。
人の手でマッサージされることで、要介護者のリラックスや幸せホルモンの分泌を促す効果も得られるでしょう。
気持ちいいと感じる程度の圧で「疲れているな」「コリがたまっているな」と感じる部分を優しくプッシュしてください。
強すぎる刺激は逆効果となる可能性があるため、要介護者の反応を見ながら力加減を調整しましょう。
ハンドマッサージについて詳しくはこちら↓
ハンドマッサージがもたらす効果は?高齢者にもおすすめのツボや方法等紹介
ストレッチ
関節の可動域を維持し、筋肉の柔軟性を保つためには寝たままできるストレッチがおすすめです。
硬くなった筋肉をほぐすことで姿勢の改善につながり、軽い負荷をかけることで可動域の維持にも役立ちます。
●おしりの筋肉のストレッチ●
- 仰向けで寝る
- 片方の膝を両手で抱える
- 膝を胴体に近づけるように引き寄せ、10秒間キープ
- 左右の脚5回ずつ繰り返す
●脇腹〜腰部の筋肉のストレッチ●
- 両脚をピッタリつけた状態で両膝を立てる
- 顔を右に向け、同時に両膝を左側に倒して10秒キープ
- 顔を左に向け、同時に両膝を右側に倒して10秒キープ
- 左右それぞれ5回ずつ繰り返す
- 左右5回ずつを2セット行う
顔を向けたほうの脇腹から腰が伸びていることを感じながら行いましょう。
筋力トレーニング
- 手のひらで「グー・パー」をする
- 足の指を「開く・閉じる」
上記は、ベッドで寝たままできる筋トレです。下肢の筋力維持と血液循環の改善に役立ちます。
また、リハビリボールの使用もおすすめです。ボールを握る、転がす、指で押すなどの簡単な運動を、疲れない程度に繰り返し行いましょう。
リハビリボールを手で握ると、握力や手指の機能維持にも効果が期待できます。
寝たきりのリハビリポイント

寝たきりの方にリハビリを実施する際に、気を付けることを解説します。
できることは自分で
リハビリの基本は、患者さんの運動機能的な自立の促進です。
介護者は、患者さんの安全を確保しながら、適度な自立支援を心がけましょう。
たとえば寝たきりの状態が続いているときは、まずベッドに自力で座ることを目指します。
起き上がる際は、最初は全面的に介助しながら、徐々に要介護者自身の力を使う割合を増やしていくといった段階的なアプローチが有効です。
できることが増えると、リハビリへのモチベーションも高まりさらなる回復につながります。
リハビリの継続
リハビリは、短距離走ではなくマラソンのように、長期的な視点で取り組むことが大切です。
初期の段階では目に見える効果が現れにくいため、焦りや諦めを感じることもあるでしょう。
毎日同じ時間に実施する、カレンダーにチェックを入れるなど、習慣化のための工夫を取り入れながら継続することが大切です。
小さな変化や進歩も見逃さず、記録につけることで、モチベーションの維持につながります。
回復には時間がかかるため、焦らず継続しましょう。
目標の設定
効果的なリハビリには、目標設定が欠かせません。
目標は要介護者と相談しながら設定し、生活スタイルや希望に沿った達成可能な目標に設定します。
短期目標(1週間程度)、中期目標(1か月程度)、長期目標(3か月以上)と段階的に設定することで、無理なくリハビリを進められるでしょう。
たとえば、短期目標は「5分間の座位保持」、中期目標は「介助での立位」、長期目標は「トイレでの排泄自立」といった具合です。
達成可能な目標を立てることで、リハビリへの意欲を高め、継続的な取り組みにつながります。
寝たきりを予防するために効果的な運動や筋トレ

健康なうちから運動や筋トレを取り入れることで、寝たきり予防につながります。
基礎体力を鍛えておけば、病気や体調不良で一時的に身体機能が衰えた際も復活しやすくなるでしょう。
ウォーキング
ウォーキングは全身の血流を促進し、心肺機能を高めると同時に、下半身の筋力を強化します。特に股関節や膝の可動域の衰えを抑制する効果を実感できるでしょう。
1日40分以上のウォーキングを週2回のペースで実施するのが理想です。
初めて運動を行う方は無理せず、まずは10分程度から始めると良いでしょう。体が慣れてきたら、徐々に時間を増やし、1日40分を目指します。
かかと上げ運動
- 足を肩幅に開いて両足のつま先を正面に向ける
- 両足のかかとをゆっくり上げてつま先で立つ
- 両足のかかとをゆっくり下げて元の状態に戻る
1日20回を目安に行います。
椅子の背もたれを持ってバランスをとりながら行ってもよいでしょう。
下半身の筋肉を優先的・集中的に鍛えると寝たきり予防につながります。
また、ふくらはぎのポンプ機能が向上し、血流が良くなることでむくみ予防や転倒防止も可能です。
ヒップリフト
- 仰向けの状態で両膝を立てて足裏を地面につける
- 両手の平を地面に置く
- 足と肩甲骨・頭で体を支えてお尻を持ち上げる
上記を10回繰り返します。
負担が大きいのであれば、できる回数から初めて10回を目指しましょう。
臀部の筋肉を強化することで骨盤の安定性が高まり、腰痛の予防にもつながります。また、重心周りが強化され、立ち上がり動作や歩行のサポートにも役立つでしょう。
スクワット
- 足を肩幅に開いて両足のつま先を正面に向ける
- お尻を後ろに引くようにゆっくり腰を落とす
- ゆっくりと腰を元の位置に戻す
スクワットは、10回を目安に行いましょう。
椅子の背もたれを使ってバランスを保ちながら行ってもOKです。
スクワットは下半身全体を鍛えるため、立ち上がりや歩行が楽になる効果が期待できるでしょう。下半身の筋力が向上することで転倒予防にもつながります。
膝や腰への負担を避けるため、正しいフォームで安全に行いましょう。
転倒予防トレーニングについて詳しくはこちら↓
【理学療法士考案】座位でもできる高齢者転倒予防トレーニングを動画つきで紹介
寝たきりからの復活にはリハビリが不可欠!無理なく取り組もう
リハビリは、寝たきりからの回復や健康寿命を伸ばすために継続的な取り組みが必要です。
寝たきりで過ごす時間が長くなると、心身機能の衰えが加速し気力も低下するためQOLが下がります。
焦らず、諦めず、着実に前進するため、できることから小さな進歩を積み重ねていきましょう。
_1.jpg)
PROFILE

カテゴリー|ブログ





 高齢者
高齢者
 高齢者
高齢者
 高齢者
高齢者
 高齢者
高齢者