訪問介護とは?特徴やサービス内容やできることとできないことを解説!料金やその他のサービスも

「訪問介護って何?」
「訪問介護でどんなサービスを受けられるの?」
など、訪問介護について知りたい方のために、情報をまとめました。
訪問介護には、サービスとしてできることとできないことがあります。
利用する前に把握すれば、利用者本人・家族ともに生活での負担を軽減できるでしょう。
訪問介護とは?
まずは、訪問介護が何か、誰が利用できるかを解説します。
訪問介護って何?
訪問介護とは、簡単にいうと訪問介護員等が利用者の居宅を訪問して、「身体介護」や「家事援助」などを提供するサービスです。
自宅以外にも、サービス付き高齢者向け住宅や住宅型有料老人ホーム、健康型有料老人ホームなど、介護サービスを提供していない施設にも訪問してもらえます。
どんな人が訪問介護を利用でき、料金がどれくらいなのか、紹介します。
訪問介護の対象者
対象者は要介護1〜5の認定を受けた人です。
要介護認定を受けていない人は利用できません。
要支援1・要支援2の認定を受けた人は、「介護予防」という目的であれば利用可能です。
要介護状態にならないための支援で、要支援1は週1回、要支援2は週2回までと、利用できる回数が決められています。
要介護認定について詳しくはこちら↓
【要介護認定のメリット・デメリット】要介護認定で受けられる公的サービスや特徴を解説
訪問介護のサービス内容

- 身体介護
- 生活援助
- 通院等乗降介助
訪問介護で受けられるサービスは、身体介護・家事援助・通院等の介助の3つに分けられます。
それぞれ詳しく見てみましょう。
身体介護
| 排泄介助 | トイレ利用・おむつ交換など |
| 食事介助 | 食事環境の整備・摂食・口腔ケアなど |
| 入浴・清拭介助 | 更衣・洗髪・洗身など |
| 移乗・移動介助 | 車椅子の準備・乗り移り・移動の介助や見守りなど |
| 起床・就寝介助 | 覚醒確認・起き上がり・ベッド上での姿勢確保など |
| 服薬介助 | 服薬の確認や促しなど |
身体介護とは、利用者の身体に直接接触して行う介護です。
排泄介助は、トイレへの誘導や衣類の着脱、排泄後の拭き取りなど排泄時のサポートやおむつ交換が含まれます。
食事介助は、エプロンをつける等環境を整え、食事を口に運ぶ、口腔ケアなど食事を補助します。
入浴・清拭介助は、自宅で入浴する際に衣類の着脱、洗髪、洗身、見守り等の他、入浴できない際の全身清拭などが含まれます。
通院等の際、車椅子の利用や移動をサポートする移乗・移動介助や、起床時と就寝時の起き上がりや体勢変更などを補助する起床・就寝介助、服薬介助も身体介護です。
生活援助
| 掃除 | 居室内やトイレなどの清掃 |
| 洗濯 | 衣類の洗濯・収納・乾燥・アイロンがけ等 |
| ベッドメイク | シーツ交換、布団カバーの交換等 |
| 衣類の整理 | 衣類の整理、被服の補修等 |
| 一般的な調理 | 配膳、後片付け等 |
| 買い物 | 日用品の買い物 |
| ゴミ出し | ゴミの分別・収集場所への廃棄 |
生活援助は、利用者本人に関する家事の支援が対象となっています。
利用者本人が利用する部屋やトイレ等の清掃、利用者本人の衣類を洗濯・収納・アイロンがけ等は、訪問介護のサービス範囲内です。
ベッドメイク、衣替え時等の衣類整理や被服の補修に加え、配膳や片付けを含めた一般的な調理も含まれます。
その他、日用品の買い物や薬の受け取り、ゴミ出しといった生活する上で必要な家事が生活援助としてサポートされるでしょう。
通院等乗降介助
| 医療機関院へ行くための準備 | 車椅子の準備や声掛け等 |
| 車や交通機関への乗降 | 病院までの移動や乗降介助等 |
| 受診等の手続き | 受付時等の対応介助 |
| 薬の受け取り | 薬局への同行や薬の受け取り等の介助 |
病院など医療機関に行く必要がある場合は、訪問介護のサービスでサポート可能です。
車椅子の準備や訪問介護員が運転する車・交通機関等の乗降を介助してもらいながら、病院まで同行してもらえます。
受け付けや薬の受取りは補助してもらえますが、院内での移動は医療サービスとなるため、看護師などが対応するでしょう。
また、交通費は訪問介護員の分も含めて利用者負担となるため、注意が必要です。
訪問介護で受けられないサービス
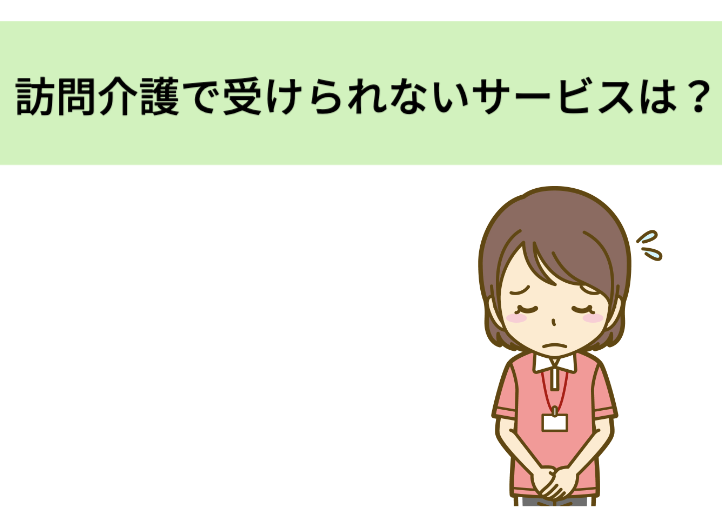
- 利用者本人以外の援助
- 日常生活を送る上で必要ない援助
- 同居中の家族がサポート可能
- 医療行為
利用者の家族に関する介護、草むしりや農作業などヘルパーがやらなくても日常生活が成り立つとされる行為に関しては介護サービスに含まれません。
訪問介護では、本人の状態に合わせて生活に支障をきたさないためのサポート全般が受けられますが、対象外となる事柄もあります。
利用者本人以外の援助
訪問介護は、利用者本人の介護や生活を補助するためのサービスです。
基本的に本人以外の援助は訪問介護のサービスにあたらないため、本人が使用していない部屋の清掃や家族分の洗濯や調理などはサポートしてもらえません。
ペットのお世話なども対象外となります。
日常生活を送る上で必要ない援助
利用者が日常生活に支障をきたさないようにサポートするのが訪問介護の目的なので、日常生活を送る上で必要ない援助は受けられません。
例えば、タバコや酒など嗜好品の買い物、窓ふきや草むしりなどしなくても困らない家事、来客対応や大掃除等特別なイベントなどに関しては、対象外です。
同居中の家族がサポート可能
訪問介護は、同居家族がいた場合でも条件を満たせば利用可能です。
家族が仕事、障害や疾病など特別な理由があって介護や援助ができない場合は訪問介護のサービスを受けられます。
しかし、同居家族がサポートできる状態であるにも関わらず「家事が苦手」「頼むのに気を使ってしまう」という理由から訪問介護のサービスを利用しようとすると、生活援助の部分で一部利用できないサービスが出てくる可能性があるでしょう。
医療行為
インスリンの注射や点滴など、医療行為となるものは訪問介護のサービスに含まれていません。
淡の吸引や経管栄養など一定の研修を受けた訪問介護員は、条件が整っていれば処置可能なものもありますが、基本的に医療行為は訪問介護のサービスではないことを知っておきましょう。
訪問介護が利用可能時間と料金
| 区分 | 利用時間 | 単位数 | 自己負担額(1割) |
| 身体介護 | 20分未満 | 167 | 167円 |
| 20分以上30分未満 | 250 | 250円 | |
| 30分以上60分未満 | 396 | 396円 | |
| 60分以上 | 579 (30分増すごとに+84) | 579円 (30分増すごとに+84円) | |
| 生活援助 | 20分以上45分未満 | 183 | 183円 |
| 45分以上 | 225 | 225円 | |
| 通院等乗降介助 | 片道 | 99 | 99円 |
訪問介護の料金は、「サービス区分×利用時間+その他(交通費等)」で1か月間の料金が計算されます。
例えば、要介護2の1割負担であり利用者が週3回1日25分の身体介護サービスを受けた場合、1か月の料金は以下のようになります。
※地域によって単位数が異なるため料金に差異が出る場合があります
訪問介護サービスを利用するまでの流れ
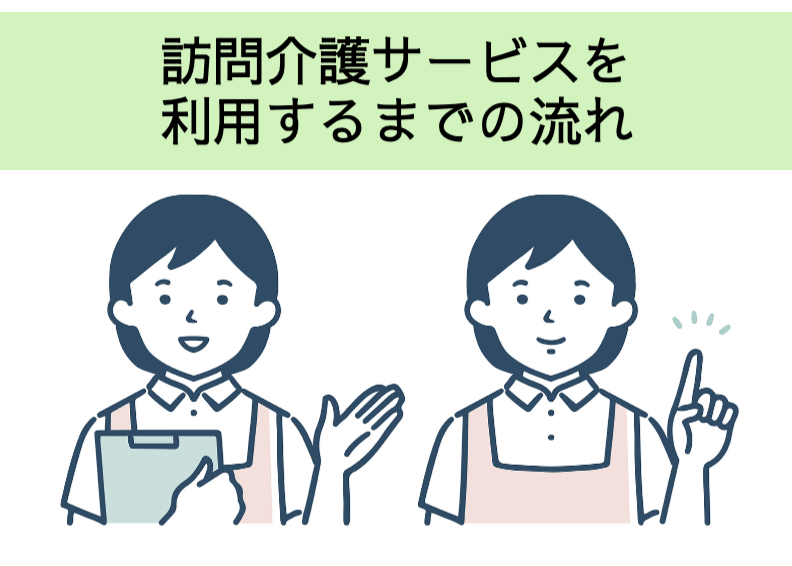
- 要介護認定を受ける
- 担当ケアマネージャーとケアプランを作成する
- 事業所を決める
訪問介護サービスを利用するには、まずは要介護認定を受ける必要があります。
大まかな流れは次の通りです。
要介護認定を受ける
- 市区町村の職員などから訪問を受け、聞き取り調査(認定調査)が行われる。
- かかりつけ医に主治医意見書を依頼する
- 認定調査結果や主治医意見書に基づき判定を経て、介護認定審査会による要介護度を決定が行われる。
- 市区町村から結果の通知がくる。
まずは、住んでいる市区町村の窓口で要介護認定の申請を行います。
申請後の流れは次のようになります。
申請から認定の通知までは原則30日以内に行われます。
ケアマネージャーとケプランを作成する
「要介護1」以上になると、ケアプラン作成事業所に依頼を出せます。
依頼後は担当ケアマネージャーが割り振られるので、どのサービスをどう利用するか、本人や家族の希望を伝えながら、介護サービス計画書を作成していきます。
担当ケアマネージャーは、本人や家族の希望により変更することも可能です。
事業所を決める
- サービスの内容や加算等について分かりやすい説明があるか
- スタッフの態度に問題がないか
- 契約に関する疑問に答えてくれるか
事業所を選ぶ際は、上記のポイントに視点を当て、少しでも疑問を感じたら担当ケアマネージャーに相談するようにしましょう。
訪問する介護職員とは利用者本人・家族ともに密接に関わることになるため、事業所選びはとても重要な部分となります。
訪問介護のメリット・デメリット
訪問介護の利用を検討する上で大事なことは、メリットとデメリットを把握することです。
メリットとデメリットを両方知っておけば、適切な段階で利用することができます。
訪問介護のメリット
- 住み慣れた自宅で過ごせる
- 施設を利用するよりも安い
- 家族の負担を軽減できる
- サービスの内容を選択できる
訪問介護最大のメリットは、住み慣れた自宅で過ごしながら介護サービスが受けられることです。
慣れない場所ではストレスを感じてしまう高齢者や、できるだけ自宅で過ごしたいと考えている高齢者の方などは訪問介護が適切でしょう。
また、施設を利用するより安く済む可能性があるため、経済的にもメリットがあります。
家族の負担を軽減できたり、利用者本人の健康状態や希望に応じてサービス内容を選択できることも、訪問介護のメリットです。
訪問介護のデメリット
- サービスが限られている
- 自宅に他人が入る
- 訪問介護員のスキルや人柄でサービスの質が変わる
訪問介護はサービス内容が選択できるものの、範囲には限りがあるため、利用者の希望がすべて叶わない場合があるでしょう。
また、自宅に家族以外の人間を入れなければならないのは訪問介護の大きなデメリットです。
そして、訪問介護員のスキルや人柄でサービスの質が左右されるため、相性などで満足なサービスとならない可能性もあります。
訪問介護事業所の選び方
- サービスと費用に関する明確な説明があるか
- 複数の事業所から話を聞いて比較する
- 利用者本人と相性がいいか
- 適切なサービスが実施されるか
訪問介護の事業所を選ぶ際は、上記4つをポイントにしましょう。
サービス内容や費用についてわかりやすい説明は、不安なく利用するための最低条件です。
内容や費用が不明瞭な事業所は選ばないようにしましょう。
また、事業所は公式サイトを見るだけでなく、複数の事業所から話を聞いて検討すると特色や雰囲気を掴めて選びやすくなります。
利用者本人との相性や、ケアプランに明記されているサービスが適切に実施されるかどうかも確認しましょう。
訪問介護以外の訪問系サービス

訪問介護以外にも、介護保険サービスとして利用できる訪問サービスがあります。
限定的なサービスを利用したい場合、役立つでしょう。
訪問入浴介護
入浴に特化した訪問サービスで、自宅の浴槽で入浴が困難な高齢者の方が利用できます。
訪問介護員が介護専用の浴槽を持参し、入浴を介護します。
訪問介護員の他にも看護職員が訪問するため、安全を確保した上で入浴が可能です。
訪問入浴について詳しくはこちら↓
訪問入浴サービスの内容|料金・通所や訪問介護との違いなど解説
訪問看護
訪問看護とは、専門の資格を持つ医療従事者が居宅要介護者に対し、療養上の世話または必要な診療の補助をするサービスです。
訪問介護との主な違いは、治療促進のための医療処置や認知症ケア、介護者へのアドバイス等が行えるという点です。
訪問リハビリテーション
訪問リハビリテーションとは、専門資格を持つリハビリ専門職員が居宅介護者の心身機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われるリハビリテーションを提供するサービスです。
訪問介護との主な違いは、機能向上を目的としたリハビリや動作指導、生活環境の提案・介護者へのアドバイスが行えるという点です。
訪問リハビリについて詳しくはこちら↓
訪問リハビリとは?在宅でできるリハビリテーションの特徴やメリット・デメリット
夜間対応型訪問介護
訪問介護員が夜間帯に利用者の自宅を訪問するサービスです。
「定期巡回」と「随時対応」があり、定期巡回は18時から8時まで定期的に訪問して排泄介助や安否確認などを行います。
随時対応は急な体調不良やベッドからの転落等のアクシデントがあった際、訪問介護員を呼んで介助や救急車の手配等をサポートしてもらいます。
夜間対応型訪問介護について詳しくはこちら↓
夜間対応型訪問介護は何時から利用できる?サービス内容や料金も解説
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護が一体的にまたは密接に連携しながら、定期巡回と随時対応を行うサービスです。
1つの事業所で訪問介護と訪問看護を一体的に提供する「一体型」と、訪問介護を行う事業者が地域の訪問看護事業所と連携をしてサービスを提供する「連携型」があります。
訪問介護で補えないサポートは介護保険外サービスで
訪問介護に限らず、介護保険では提供されないサービスを受けたい際は、介護保険外サービスの利用を検討しましょう。
介護保険外サービスとは、介護認定を受けている受けていないに関わらず利用できるサービスです。
どんなサービスがあるか、例を紹介します。
介護保険外サービスについて詳しくはこちら↓
介護保険外サービスって何?種類や料金を事例付きで紹介!
自治体の高齢者在宅サービス
おむつの配送や訪問理美容サービス、配食サービスなど、各自治体が高齢者向けに提供しているサービスがあります。
自治体によって内容は異なるため、お住いの市区町村に確認してみましょう。
葛飾区で訪問美容を利用したい方はこちら↓
葛飾区の訪問カットならヘアサロンりふり
介護サービス事業者の介護保険外サービス
デイサービスなど介護サービスを提供している事業者が、自費リハビリや生活援助、お泊りデイサービスなどを提供していることがあります。
介護保険の範囲では補えないサポートが必要な場合など、利用を検討しましょう。
自費リハビリについて詳しくはこちら↓
自費リハビリって何?保険適用内との違いや効果・料金・注意点など解説
民間企業のサービス
家事代行サービスや見守りサービスなど、民間企業は幅広いサービスを提供しています。
市区町村などが提供しているものより費用がかかりますが、充実した内容から場合に応じて選択できるのが魅力です。
訪問介護サービスを活用して、本人・家族ともに負担の少ない生活を
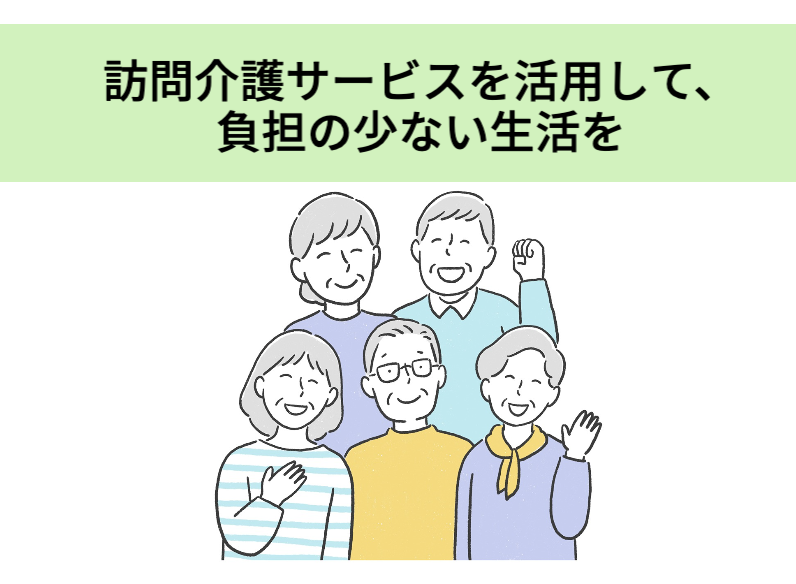
訪問介護は、利用者の居宅を訪問して介護や生活援助などを提供するサービスです。
利用者本人に関わる介護や掃除などの家事、通院のサポートなどを行います。
家族分の洗濯など、利用者以外の家事や、タバコなどの嗜好品の買い物や来客対応といった本人の日常生活に支障をきたさない部分の作業は行えません。
住み慣れたところで介護サービスを受けられるなどメリットはありますが、限られたサービスしか受けられないなどのデメリットもあります。
介護保険外サービスなども利用しながら、適切に訪問介護を利用すると本人・家族ともに負担の少ない生活が送れるでしょう。
カテゴリー|ブログ





 高齢者
高齢者
 高齢者
高齢者
 高齢者
高齢者
 高齢者
高齢者