要介護認定に証明書がある?「介護保険被保険者証」の受け取り方や再発行方法など
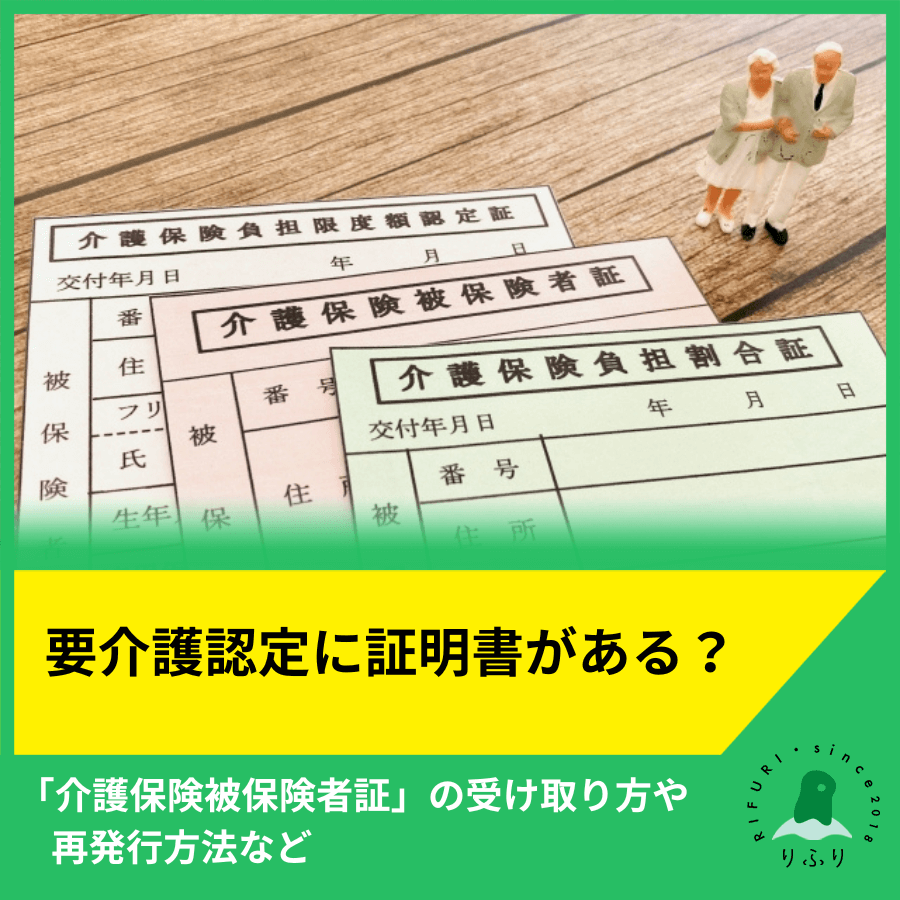
「要介護認定の証明書って何?」
「介護保険被保険者証って何だろう?」
など、要介護認定の証明書について知りたい方のために、介護保険被保険者証の概要についてまとめました。
介護保険被保険者証とは何か、どんなときに使うのか、受け取り方や発行方法などについて詳しく解説します。
要介護認定の証明書って?
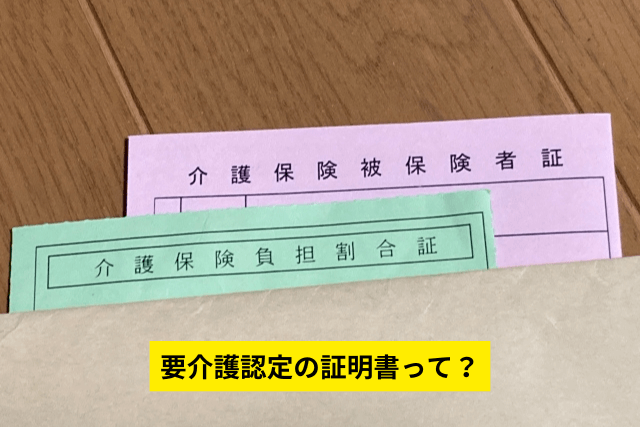
要介護認定の証明書とは、正式名称を『介護保険被保険者証』といいます。「介護認定証」や「介護保険証」と呼ばれることもあり、さまざまなシーンで公的な証明書として扱われるものです。
介護保険被保険者証について、詳しくご紹介します。
要介護認定について詳しくはこちら↓
要介護認定とは?区分や判定基準・申請から要介護度決定までの流れなどを解説
介護保険被保険者証とは?
介護保険被保険者証は介護保険の加入者であるという証明書です。65歳以上の全国民、あるいは特定疾病により要介護認定された40~64歳の国民に交付されます。
保険料の加入状況や加入資格を確認する際や、要介護認定を受ける際などに必要な証明書です。交付された際は、大切に保管しておきましょう。
介護保険被保険者証に書いてあること
- 被保険者の情報
- 要介護の区分
- 認定年月日と有効期限 など
介護保険被保険者証には被保険者の氏名や住所、生年月日など基本的な情報が記載されています。また、要介護認定を受けた場合は「要支援1・2」「要介護1~5」など認定された区分や認定年月日が追記されるでしょう。
要介護認定の有効期限や在宅サービスの利用限度額なども記載されるため、ケアマネジャーや介護事業所が介護保険サービス利用の適否を確認するのに不可欠です。
介護認定審査会がサービス提供上の留意点など必要な意見を付した場合や、保険料の滞納などにより給付制限を受けている場合などは、その内容も明記されています。
介護保険被保険者証はいつ発行される?
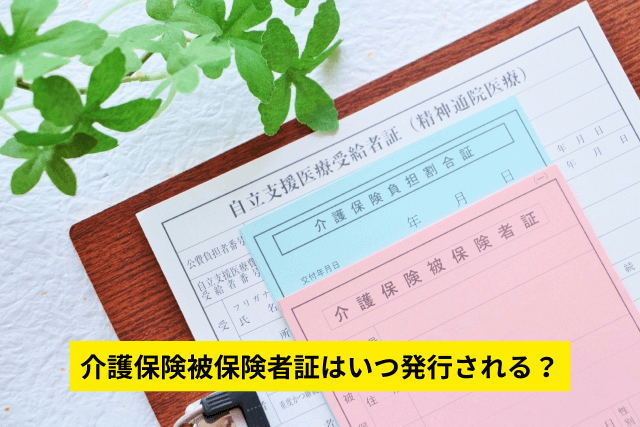
- 65歳の誕生月
- 40歳から64歳までで要介護認定を受けたとき
介護保険被保険者証が発行されるタイミングは、上記2つのパターンがあります。それぞれについて、見ていきましょう。
65歳の誕生月
65歳の単曜日になると、自動的に市区町村から介護保険被保険者証が交付されます。特に申請などは必要ありません。
日本では65歳以上が介護保険の第1被保険者と定められており、介護の必要性がなくても「介護保険の加入者」という証明書として介護保険被保険者証を持つことになります。
情報確認のために提示を求められたり、要介護認定の申請や介護保険サービスの利用で必要になったりするでしょう。
40歳から64歳までで要介護認定を受けたとき
40歳以上65歳未満であっても、16の特定疾病により要介護状態または要支援状態と認定された場合は第2号被保険者となり、要介護認定の結果が確定した時点で介護保険被保険者証が交付されます。
要介護認定区分や有効期間なども記載されている状態で交付され、第2号被保険者であることの証明だけではなく、要介護認定の結果を証明する役割も担うことになるでしょう。
要介護認定を受けるタイミングについて詳しくはこちら↓
要介護認定を受けるベストなタイミングは?入院中の場合やとりあえず認定される際に注意点
介護保険被保険者証を使うとき
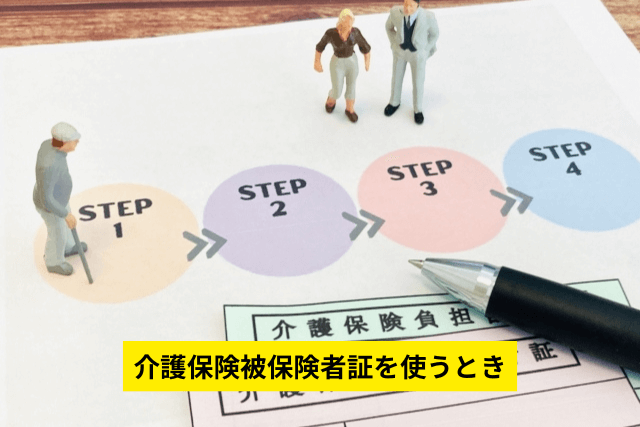
- 要介護認定の申請をするとき
- ケアプランを作成するとき
- 介護保険サービス事業者と契約するとき
- 介護給付金を申請するとき
- 要介護認定の更新や区分変更の手続きをするとき
介護保険被保険者証を使う場面は、主に上記のとおりです。一つずつ、詳しく解説します。
要介護認定の申請をするとき
新規で要介護認定を申請する際には、介護保険被保険者証をはじめいくつかの書類を市区町村に提出しなければなりません。
介護保険被保険者証を提出すると、市区町村は申請者が介護保険の被保険者であり、申請資格が有ることを確認できます。介護保険被保険者証がないと再発行など別の手続きが必要になる可能性があり、要介護認定の申請がスムーズにいかない場合があるでしょう。
要介護認定の申請について詳しくはこちら↓
要介護認定を申請できる人はこんな人!条件や必要なものなど解説。本人以外の申請は?
ケアプランを作成するとき
要介護認定を受けたあと、介護保険サービスを利用するためにはケアプランを作成する必要があります。介護保険被保険者証は、要介護認定の区分や有効期限など極めて重要な情報が記載されているため、ケアプラン作成に欠かせません。
ケアプランは、ケアマネジャーが要介護者と家族の希望や心身の状態、生活環境を踏まえてどのような介護サービスを利用するかについて計画する書類です。要介護者の要介護度などの情報が正しく確認できなければ、ケアプランを作成できません。
必要な情報が正確にわからなければケアプランは有効な計画書として成立しないため、介護保険被保険者証は最も重要な資料となります。
介護保険サービス事業者と契約するとき
介護保険サービスを実際に利用するには、ケアプランの内容に基づいて必要なサービスを提供してくれる介護保険サービス事業者と契約を結ばなければなりません。契約時に必要となるのが、介護保険被保険者証です。
介護保険サービス事業は、契約時に申込者が介護保険サービスを利用する権利があることを確認しなければなりません。介護保険被保険者証を提示しなければ、介護保険が適用されずに費用の全額が請求されることもあります。
要介護認定を受けたあと介護保険を使わない場合について詳しくはこちら↓
介護保険は使わないと損?要介護認定を受けたけど使わないとどうなる?
介護給付金を申請するとき
介護保険制度における給付金の申請には、介護保険被保険者証の提出が必須です。たとえば、要介護認定を受けると特定福祉用具の購入や住宅改修の費用が一部償還払いされます。
その給付金を申請する際、介護保険被保険者証がないと給付を受ける資格があることを証明できません。申請自体が受理されないため、必ず介護保険被保険者証を提出しましょう。
要介護認定の更新や区分変更の手続きをするとき
要介護認定には有効期間が定められており、原則として新規認定の場合は6か月、その後は12か月ごとの更新が必要です。更新申請を行う際には、申請者が被保険者であることや現在の認定区分を確認するために介護保険被保険者証の提出が求められます。
また、疾病の進行などによって心身の状態に変化が出れば、要介護度を変更するための区分変更申請が必要です。区分変更申請にも介護保険被保険者証を提出しなければならず、要介護認定関連の手続きには常に必須であると考えておきましょう。
要介護認定を受けるメリット・デメリットについて詳しくはこちら↓
とりあえず要介護認定だけ受けるべき?メリットデメリットや介護保険の賢い使い方
介護保険被保険者証の再発行方法

- 窓口での申請方法
- 郵送での申請方法
- オンラインでの申請方法
紛失などで介護保険被保険者証を再発行したい場合は、上記3つの方法があります。それぞれの申請方法について詳しくご紹介します。
窓口での申請方法
- 介護保険被保険者証再交付申請書
- 本人確認書類※代理申請は代理金の本人確認書類
- 委任状※代理申請の場合
市区町村の窓口に行くと、介護保険被保険者証の再交付手続きができます。窓口に本人が行けない場合は、代理人が申請手続きを行うことも可能です。
本人が手続きする場合は「介護保険被保険者証再交付申請書」「本人確認書類」が必要となり、代理人が手続きする場合は、代理人の本人確認書類に加えて委任状が必要でしょう。
ただし、市区町村によって提出書類が異なるため、事前に確認しておくと安心です。
郵送での申請方法
- 介護保険被保険者証再交付申請書
- 本人確認書類※代理申請の場合は代理人の本人確認書類
- 委任状※代理申請の場合
郵送で介護保険被保険者証の再発行を申請する場合は、上記の書類を市区町村の役所に郵送します。
窓口に出向くことが難しい高齢者や家族にとって便利な申請方法です。新しい介護保険被保険者証が手元に届くまで、1週間から10日ほどかかるといわれています。
郵送での申請は多くの自治体で対応している場合が多いですが、郵送申請の可否や詳細な提出先は事前に市区町村に問い合わせたりホームページで確認したりしましょう。また、提出書類は各自治体で異なる場合があるため、何が必要になるのか確認しておくことをおすすめします。
オンラインでの申請方法
- マイナンバーカード
- 署名用電子証明書暗証番号
- スマートフォン
一部の自治体では、オンラインでの申請が可能となっています。オンラインで申請する場合はマイナンバーカードを使って個人認証をするため、申請者のマイナンバーカードや署名用電子証明書暗証番号、マイナンバーカードをスキャンできるスマートフォンなどが必要です。
オンライン申請は自治体によって利用できるシステムや、代理人登録の手順が異なります。市区町村の公式サイトなどで具体的な手順を確認して実施しましょう。
介護保険被保険者証でスムーズな介護の手続きを
要介護認定の証明書と呼ばれる介護保険被保険者証は、介護保険サービスを受けるための大切な身分証です。介護保険の加入者であることを証明でき、65歳以上の人あるいは40歳以上65歳未満で16の特定疾病により要介護状態または要支援状態と認定された人に市区町村から交付されます。
介護保険被保険者証は、要介護認定の申請時やケアプラン作成時、介護保険サービス事業者との契約時、介護給付金の申請時などに必要です。介護保険被保険者証を提示すれば、介護保険サービスの受給資格があることを証明でき、1~3割の自己負担額でサービスを受けられるほか、各種手続きがスムーズに進むでしょう。
必要なときにすぐに提出できるように、日ごろから大切に保管しておきましょう。
_1.jpg)
カテゴリー|ブログ





 高齢者
高齢者
 高齢者
高齢者
 高齢者
高齢者
 高齢者
高齢者