訪問リハビリとは?在宅でできるリハビリテーションの内容や費用・メリットデメリット

「訪問リハビリは誰が利用できる?」
「訪問リハビリはいくらかかる?保険は使える?」
訪問リハビリは、自宅で専門的なリハビリテーションを受けられるサービスです。
通院の負担なく、慣れた環境で効果的なケアが受けられると注目を集めています。
利用方法や費用感は実際どうなのでしょうか。
この記事では、訪問リハビリの特徴や対象者、費用、メリット・デメリットなどを詳しく解説します。
訪問リハビリについて知りたい方は、ぜひご覧ください。
訪問リハビリとは?特徴や対象者

訪問リハビリは、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士などフィジカルケアの専門職が利用者の自宅を訪問し、リハビリテーションを行います。
自宅という馴染みの環境で行うため、利用者の生活に即したリハビリが可能です。
対象者は、主に要介護・要支援認定を受けた高齢者や、障害のある方々です。
脳卒中後遺症、整形外科的疾患、廃用症候群など、さまざまな方が利用できます。
リハビリの専門家が定期的に訪問し、身体機能の維持・改善を目指すだけではなく、自宅を生活しやすい環境に整えるアドバイスも行います。
訪問リハビリでできること
- 心身機能の維持・回復
- 日常生活の自立支援
- 健康管理
- 家族に対する介護・介助方法の指導や助言
- 福祉機器・用具などの提案
訪問リハビリでは、上記のようなサポートが可能です。
まず、心身の機能の維持・回復を目指し、筋力トレーニングや関節可動域訓練などを行います。
日常生活の自立支援として、歩行や入浴、食事などの動作練習を実施、定期的な健康管理や、家族に対する介護・介助方法の指導や助言も重要な役割です。
生活環境に合わせた福祉機器・用具の提案や調整を行い、より安全で快適な生活をサポートします。
利用者一人ひとりのニーズに合わせて、専門的かつ総合的なリハビリテーションを行い、可能な限り自宅で自立生活を送れるように手助けするのが訪問リハビリです。
訪問リハビリが受けられる人
- 要介護認定を受けている方
- 在宅でのリハビリが必要と主治医が判断した方
訪問リハビリは上記2つの条件を満たしている人が受けられます。
まず、要介護認定を受けており、要介護1~5の介護度が割り当てられていることが条件です。
また、担当医から「訪問リハビリが必要」と診断されている必要があります。医師の指示書がなければ、サービスを受けることはできません。
上記2つの条件を満たす方であれば、疾患の種類に関わらず訪問リハビリテーションを受けられます。
要支援1~2の方も、要介護状態への進行予防の名目で訪問リハビリの利用が可能です。
訪問リハビリにかかる費用

| 区分 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 要支援1 | 1,260円/月 | 2,520円/月 | 3,780円/月 |
| 要支援2 | 1,280円/月 | 2,560円/月 | 3,840円/月 |
| 要介護1・2 | 1,336円/月 | 2,672円/月 | 4,008円/月 |
| 要介護3 | 1,344円/月 | 2,688円/月 | 4,032円/月 |
| 要介護4 | 1,348円/月 | 2,696円/月 | 4,044円/月 |
| 要介護5 | 1,328円/月 | 2,656円/月 | 3,984円/月 |
介護保険を使って訪問リハビリを月に4回利用した場合、かかる月額費用は上記のとおりです。
訪問リハビリの費用は、利用者の要介護度や利用回数によって変動します。
たとえば週1回の頻度で月に4回利用した場合の費用は1,000円〜4,000円程度です。
介護保険を利用すると収入に応じて1割~3割の自己負担となります。
ただし、あくまで目安であり、実際の費用は事業所や地域などによって異なります。
参考:概算料金の試算 | 介護事業所・生活関連情報検索「介護サービス情報公表システム」
訪問リハビリ利用方法|介護保険・医療保険が使える?
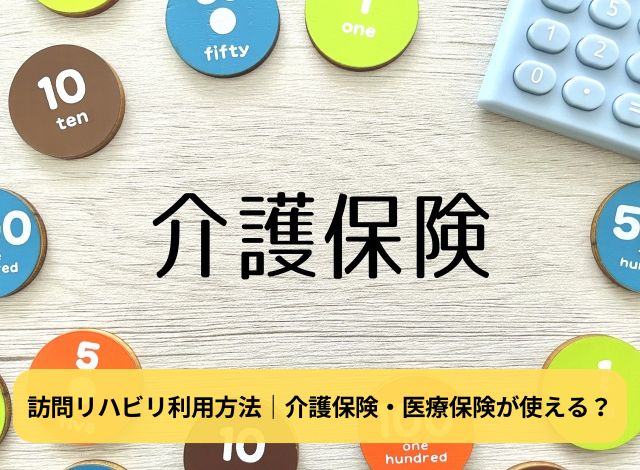
| 年齢区分 | 要介護・要支援認定を受けていない場合 | 要介護・要支援認定を受けている場合 |
|---|---|---|
| 40歳未満 | 医療保険 | 医療保険 |
| 40歳~64歳 (第2被保険者) | 医療保険 | 原則医療保険(特定疾病の場合は介護保険) |
| 65歳以上 (第1被保険者) | 医療保険 | 介護保険 |
上記は要介護・要支援認定の有無と年齢に応じた保険適用の状況を表にまとめたものです。
訪問リハビリは、介護保険と医療保険の両方で利用可能ですが、併用はできません。原則として介護保険が優先です。
介護保険で利用する場合は、要介護認定を受けた上でケアプランに組み込む必要があります。
一方、医療保険での利用は、主に介護保険対象外の方や特定疾病の方、64歳までの方が対象です。
どちらの保険を使うかは、利用者の状況や医師の判断によって決定されます。
介護保険で利用する場合
- 要介護認定を受ける
- ケアマネジャーに相談し、利用したい事業所があれば伝える
- 医師が訪問リハビリを必要と判断し、指示書を発行する(3か月に1回受診が必要)
- 事業所と契約
- 訪問リハビリ開始
介護保険での訪問リハビリ利用は、上記の手順で進みます。
まず、要介護認定を受けます。認定結果が出たら、ケアマネジャーに相談し、利用したい事業所があれば伝えます。
次に、医師の診断を受け、訪問リハビリが必要と判断されれば指示書を発行してもらいます。指示書は3か月に1回の更新が必要です。
その後、事業所と契約を結び、訪問リハビリを開始します。
なお、40歳以上65歳未満の方は、特定疾病に該当する場合のみ介護保険が利用できるため、該当する場合は要介護認定の申請が必要です。
医療保険で利用する場合
- 医師が訪問リハビリを必要だと判断し、指示書を発行する。(1か月に1回受診が必要)
- ケアマネジャーを介さず、事業所や医療機関と直接契約を行う。
- 訪問リハビリ開始
医療保険での訪問リハビリ利用は、介護保険と比べてやや簡略化されています。
まず、医師の診断を受け、訪問リハビリが必要と判断されれば指示書を発行してもらいます。医療保険の場合、指示書は1か月に1回の更新が必要です。
次に、ケアマネジャーを介さず、直接事業所や医療機関と契約を行います。その後、訪問リハビリを開始します。
医療保険での利用は、65歳未満の方で介護保険の対象とならない方や、65歳以上でも、介護保険の認定を受けていない方が対象です。
訪問リハビリのメリット・デメリット

訪問リハビリには、自宅で受けられる便利さがある一方で、一定の制約もあります。以下では、そのメリットとデメリットを詳しく見ていきます。
訪問リハビリのメリット
- 通うのにかかる時間・手間・交通費不要
- 慣れた環境でのリハビリが可能
- より生活に則した実践的リハビリが可能
- 家族も一緒に指導を受けられる
- 自宅の状況に合わせたリハビリを受けられる
訪問リハビリの大きなメリットは、通院の負担がないことです。
通うのにかかる時間・手間・交通費が不要で、体力的な負担も減らせるでしょう。
また、慣れた環境でのリハビリが可能なため、心理的な安心感も得られます。
さらに、より生活に則した実践的リハビリが可能となり、QOLの改善に直結しやすいのも大きなメリットです。
加えて、家族も一緒に指導を受けられるため、日常的なケアの質向上も見込めるでしょう。
自宅の環境に合わせた具体的なアドバイスも受けられ、生活空間の安全性を高めることも可能です。
訪問リハビリのデメリット
- 他人が家に出入りする
- リハビリ内容が限られる
- 他の利用者と交流できない
- 家族の負担になる可能性
訪問リハビリには一定のデメリットもあります。
まず、他人が家に出入りすることへの抵抗感や、プライバシーの問題が挙げられます。
また、リハビリ内容が自宅でできる範囲に限られるため、大型の機器を使用するような高度な治療には向いていません。
そのため使用できる器具や環境が制限され、施設で行うリハビリと比較して効果が限定的になる可能性があります。
さらに、他の利用者との交流の機会が少なくなり、社会性の維持が課題となるかもしれません。
加えて、家族の協力を得られることはメリットでもありますが、負担になるという一面もあります。
訪問介護は自宅にいながら専門的ケアが受けられます
訪問リハビリは、リハビリの専門家が自宅を訪れて行う、一人ひとりに特化したリハビリテーションサービスです。
心身機能の維持・回復から日常生活の自立支援まで、幅広いケアが可能です。
通院の負担がなく、生活に即したリハビリができる一方で、プライバシーや内容の制限といった課題もあります。
訪問介護は一人ひとりの状況に応じて検討し、適切に活用することで、在宅生活の質を大きく向上させる可能性を秘めています。
リハビリの効果を高めたいと考えている方は、ぜひケアマネジャーや医療機関に相談し、自分に最適なリハビリプランを見つけてください。
カテゴリー|ブログ





 リクルート
リクルート
 高齢者
高齢者
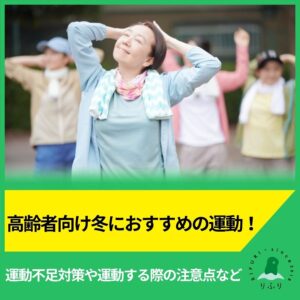 高齢者
高齢者
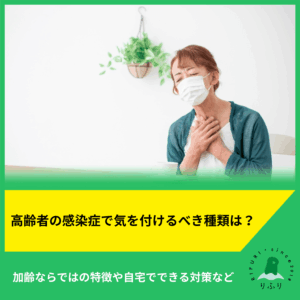 高齢者
高齢者