高齢者の低体温症は命に関わる?注意すべき症状や原因・対処法・対策など

「高齢者の低体温症ってどんな症状?」
「高齢者は低体温症になりやすい?」
など、高齢者の低体温症について調べている方のために、低体温症の基本情報についてまとめました。高齢者にとって、低体温症は健康上見過ごせないリスクとなります。
高齢者が低体温症に注意すべき理由や早期に気付くためのサイン、予防のためにできる工夫について分かりやすく解説するため、ぜひ参考にしてください。
高齢者の冬の過ごし方について詳しくはこちら↓
冬の過ごし方や注意点│高齢者は寒がり対策や運動で健康管理に気を付けて
低体温症について

低体温症は高齢者にとって命の危険に関わる状態です。低体温症とは何なのか、低体温との違いについて解説します。
低体温症とは?
低体温症とは、深部体温が35℃を下回る状態をいいます。深部体温とは、内臓や脳など体の中心部分の温度です。
通常、人間の深部体温は37℃前後で保たれており、適切な深部体温を保つことで臓器や代謝機能が正常に働いています。
深部温度が低下すると体の機能に重大な支障をきたし、進行すると死に至る危険もあるでしょう。
低体温症と低体温の違い
低体温症は深部体温が35℃未満に低下した状態であり、意識障害、呼吸・心拍の低下など命に関わる機能障害を伴うこともある医学的な緊急状態です。
一方、低体温は脇の下で測る体温が36℃以下など、平熱が一般より低い状態を指しています。病的な異常ではありませんが、免疫力の低下などの不調を引き起こしやすくなるといわれているため、注意が必要です。
高齢者が低体温症に気をつけるべき理由
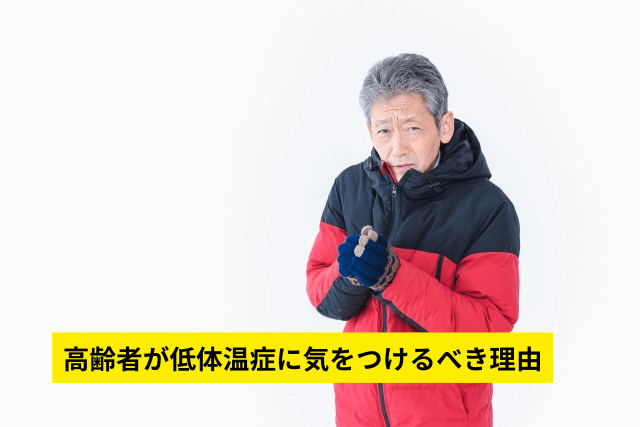
- 進行すると命に関わる
- 回復後にADL(日常生活動作)が低下する可能性がある
- 室内でも起こり得る
高齢者は特に低体温症に気をつけなければならないといわれています。その理由を、3つに分けて詳しくご紹介します。
進行しやすい
高齢者は熱を生み出す機能や体温を保持する機能が低下している場合があります。一度低体温症になると進行が速く、重篤な状態になってしまうケースが少なくありません。
早期の発見と予防が極めて重要であり、そのためには低体温症について知識を付けておく必要があります。
回復後にADL(日常生活動作)が低下する可能性がある
高齢者の場合、低体温症から回復した後にADL(日常生活動作)が低下する可能性が高くなるといわれています。低体温症で入院すると病状によっては安静期間が長くなり、筋力や身体機能が急速に低下してしまうでしょう。
加齢により筋肉量が減っているサルコペニアの状態であれば、入院によってさらに筋力や持久力が落ちて日常生活に支障をきたすことが少なくありません。
また、低体温症の進行で各臓器に障害が起これば脳や心臓などに影響がおよび、回復後も認知機能や身体機能に影響を残すことがあります。
室内でも起こり得る
低体温症は屋外の寒い環境で起こると思われがちですが、実は高齢者の場合は室内でも発症するリスクがあります。実際、日本救急医学会による研究では、低体温症を発症する場所は屋外よりも屋内が約3倍も多かったとのことです。
冬の室内は寒暖差が大きく、体が急激に熱を奪われる場面が多くなります。高齢者は体温を調整する機能が低下している傾向にあり、急激な体温変化に対応できず体が熱を失ってしまうため、深部体温が急降下しやすいといわれています。
また、ヒートショックなどを引き起こしてその場から動けなくなると、寒いところで長時間さらされてしまうこともあるでしょう。高齢者は熱を生み出す機能が弱まっていることが多く、体温が奪われ続ければ低体温症になる可能性が高くなります。
高齢者のヒートショックについて詳しくはこちら↓
高齢者のヒートショックとは?メカニズムや予防策・緊急時の対処法など
高齢者はなぜ低体温症になりやすい?
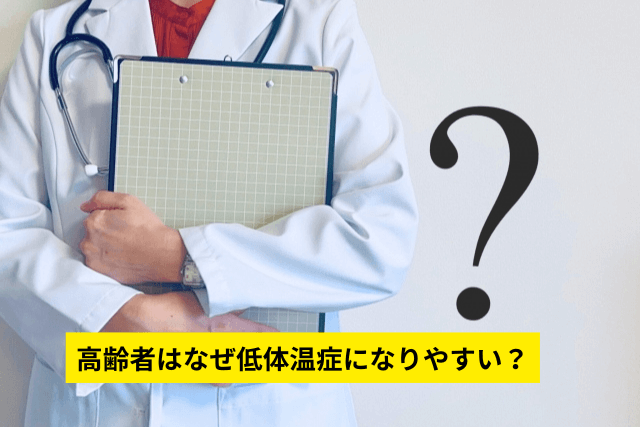
- 保湿機能低下
- 薬や持病の影響
- 生活習慣
高齢者が低体温症になりやすいのは、主に上記3点が理由に挙げられます。
保温機能低下
高齢者は加齢によって体温調節機能が低下していおり、気温の変化に体が適応できず、体温を維持しにくくなっているため、低体温症になりやすいといわれています。
また、高齢者は若い頃よりも筋肉量が減少しているのが特徴です。筋肉は熱を生み出す組織であり、筋肉量が減少すると体内での熱産生量が低下するため体温が下がりやすくなります。
活動量や食事量が少なくなっている高齢者の場合は特に体に必要な熱を十分に生み出せないため、気付いたら低体温症を発症しているケースが少なくありません。
薬や持病の影響
服用している薬や持病の影響は、低体温症の発症に大きく関与することがあります。抗うつ薬など特定の薬は体温調節機能に影響を与える可能性があるため、服用している場合は注意が必要です。
糖尿病や甲状腺機能低下症、心疾患や血液疾患などは低体温症のリスクが高いといわれています。糖尿病は体温を調節する役割がある自律神経の働きに影響を及ぼし、甲状腺機能低下症は体温を調節する働きがある甲状腺ホルモンが減少するため、十分な熱を産生できなくなるからです。
心臓や血液の疾患では血流が悪くなって熱産生量が減少し、リスクが高くなります。
生活習慣
高齢になると食べる量が減るケースは少なくありません。食事の消化や吸収、代謝のために使われるエネルギーが熱となって消費される作用を「食事誘発性熱産生」といいます。食事誘発性熱産生は体温の維持を助ける重要なメカニズムですが、加齢とともに食事の摂取量が少なくなると発生する熱も少なくなり、体が温まりにくくなるでしょう。
食事量の減少でタンパク質やエネルギーの摂取量が減ると体温調節に必要な筋肉量が減り、低体温症のリスクが高まることもあります。
また、外出の頻度が減るなど運動不足になる高齢者は少なくありません。運動不足になると筋肉量が減り、体内での熱産生が十分に行われず、体温を維持しづらくなります。
高齢者の中には、光熱費を抑えようとして暖房の使用を控える人もいるでしょう。我慢すれば大丈夫と思ってエアコンやストーブを使用しないまま過ごしていると、室内にいても気づかないうちに低体温症のリスクが高まっている可能性があります。
高齢者の低栄養について詳しくはこちら↓
食べているのに高齢者が低栄養になる原因や対策、アルブミンを上げる食事など紹介
高齢者の低体温症はどんな症状が出る?
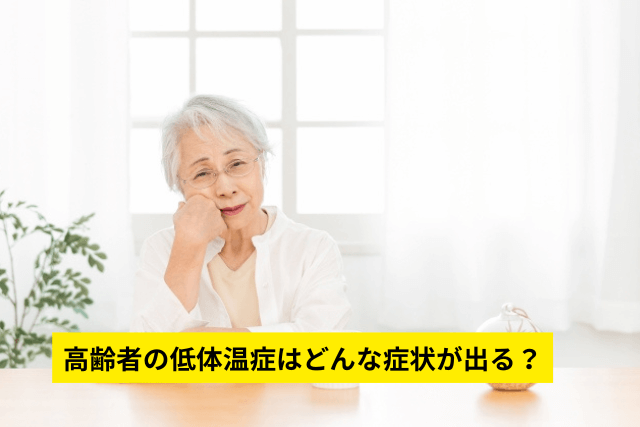
- 体温低下が見られるのに震えがない
- 応答が遅い・ぼんやりしている
- 血色が悪く呼吸に変化がある
高齢者が低体温症になると、主に上記3つの症状が現れます。それぞれについて詳しく見ていきましょう。
体温低下が見られるのに震えがない
一般的に、低体温症の初期症状では体の震えが見られますが、高齢者は体の震えが起こらないことがあります。体の震えは、体が熱を作り出すために筋肉を無意識かつ急速に収縮・弛緩させることで起こる症状です。
しかし、高齢者は筋肉量の減少などによって、体温が下がっていても震えが起こりにくいという特徴があります。
体温低下が見られるのに「震えがない」こと自体を低体温症のサインと捉え、早めに対応しましょう。
応答が遅い・ぼんやりしている
体温の低下とともに話しかけても反応が遅くなる、ぼんやりする、動作が遅くなるなどの症状が現れることがあります。体温の低下とともに中枢神経機能が鈍くなり、思考力や判断力などが低下するからです。
さらに低体温症が悪化すると昏睡状態に陥って内臓の働きが悪くなり、体温維持が難しくなります。いつもの状態が鈍化したり、不自然に無口・不活動になったりしたときは低体温症を疑いましょう。
血色が悪く呼吸に変化がある
高齢者が低体温症になると、血管の収縮により血色が悪くなり、体の代謝低下により呼吸にも変化が現れます。
低体温症になると体温を保とうとして熱が逃げやすい皮膚の血管を強く収縮させるため、皮膚への血流が減って唇や爪の色が紫色になることがあるでしょう。
指先への血流も減ることから、指先の感覚が麻痺することもあります。
血色が悪い場合は本人が寒さを訴えていなくても、手足の冷たさや感覚の有無を確認して低体温症かどうか確認しましょう。
また、体温が低下するにつれて呼吸が浅くなり、呼吸回数が減ります。症状が悪化すると死に至る場合があるため、呼吸の変化を見落とさないようにしましょう。
高齢者で低体温症が疑われる場合の対処法
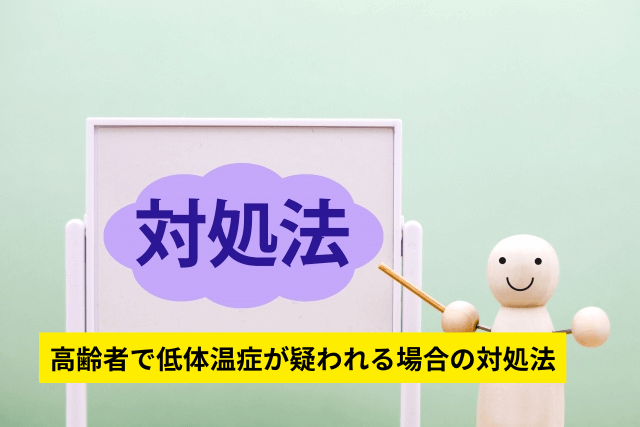
- 暖房が効いた部屋に移動
- 体を毛布などで温める
- 水分・栄養補給
高齢者に低体温症の疑いがあるときは、上記3つの対処法を行いましょう。一つずつ詳しくご紹介します。
暖房が効いた部屋に移動
高齢者で低体温症が疑われる場合、まずは暖房が効いた部屋に移動させましょう。寒い室内や屋外で長時間過ごすと体の熱が奪われ続け、体温の低下が進行するおそれがあります。暖かい場所で安静にさせて、それ以上体温を低下させないようにすることが第一の対応です。
衣服が汗などで濡れている場合は、すぐに乾いたものに着替えさせましょう。衣服が濡れていると、水分が蒸発するときに気化熱の作用で体の熱が奪われ、急速に体温が下がる可能性があるからです。
体を毛布などで温める
体を毛布や防寒着などで包み込み、外部からの熱喪失を防ぎましょう。低温やけどに気を付けながら、カイロや湯たんぽを使うと効率よく体を温められます。
カイロや湯たんぽを使う際は、心臓に近い首や心臓、脇の下、おへその下などを中心に温めると効果的です。逆に、手足の先など体の先端を温めると手足からの冷たい血液が心臓に流れ込み、体温が急激に低下してショック状態を引き起こす可能性があるため、手足を温めるのは避けましょう。
水分・栄養補給
意識がはっきりしていてむせることなく飲食ができる状態であれば、温かい飲み物を摂取させると効率よく体温を上げられます。温かいお茶やココア、スープや味噌汁など飲みやすいものが最適です。
カフェインが含まれる紅茶やコーヒー、アルコールには利尿作用があり、脱水症状を引き起こすおそれがあります。体の熱を逃してしまうため、避けましょう。
また、低体温症になると中枢神経の働きが低下する可能性があり、固形物を摂取させるのは避けるのがベストです。
体を温める飲み物について詳しくはこちら↓
体を温める飲み物紹介!冬に飲みたいものや寝る前・風邪のときに良いもの等を解説
高齢者の低体温症で救急車を呼ぶべき場合や禁止事項
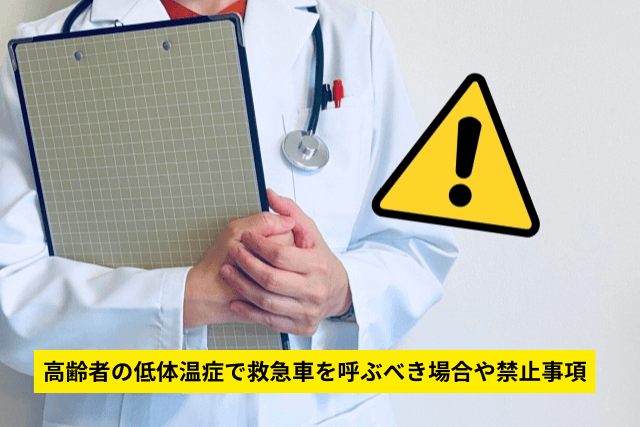
- 意識レベルの低下が見られたら救急車を呼ぶ
- 急激な加温は避ける
- 意識レベルの低下が見られたら体を動かさない
高齢者が低体温症になったとき、救急車を呼ぶべき状態や行ってはいけない対応を正しく理解しておくことが大切です。いざというときに慌てないために、具体的なポイントについて解説します。
意識レベルの低下が見られたら救急車を呼ぶ
ぐったりしている、呼びかけに応答しないなどの症状がみられる場合、すぐに救急車を呼びましょう。体温低下による意識障害の可能性が高く、体が危険な状態にあるサインだといえます。
高齢者は急速に昏睡状態へと悪化するケースもあるため、速やかな対応が重要です。
顔面蒼白の症状や寒がっているのに震えが止まっているという場合も、危険な状態であることが多く、早急に救急車を呼ぶ必要があります。
急激な加温は避ける
温かい風呂に入れる、ヒーターを直接あてる、手足をマッサージするなど、急激に体を温める行為は避けましょう。血流が再開した際に冷えた血液が急に心臓に戻ると、心臓に負担がかかってショック状態になるおそれがあるからです。
また、急激に体を温めると血圧が急降下して、体に負担となる可能性もあります。毛布や湯たんぽ、カイロなどの温熱剤を使って体の中心部をゆっくり温めるのがポイントです。
意識レベルの低下が見られたら体を動かさない
体を揺すったり無理に動かしたりする行為は非常に危険です。重度低体温症の場合、心臓の筋肉はデリケートになっており、少しの刺激でも不整脈を引き起こす危険があります。
最悪の場合、心臓が停止する可能性もあるため、呼びかけに対する反応が鈍いなど意識レベルの低下が見られたら体を動かさずにその場で保温し、救急車を呼びましょう。
高齢者の低体温症予防
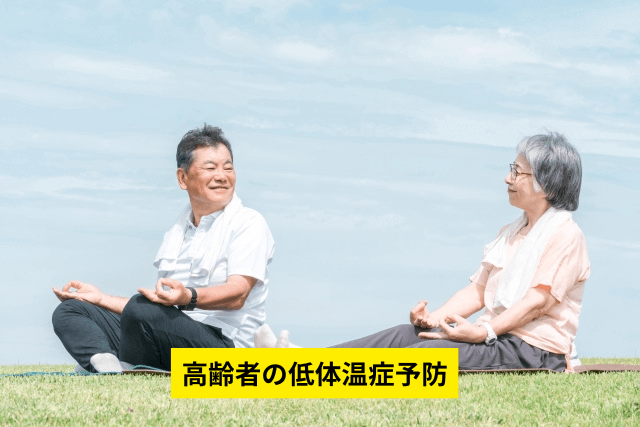
- 室温管理
- 体を温める食事を心がける
- 運動習慣を身に付ける
低体温症は生活習慣や環境の工夫で対策が可能です。高齢者の低体温症を予防する方法を3つ、ご紹介します。
室温管理
低体温症は室内でも起こり得るため、冬場は室温管理が重要です。夏は冷房のかけすぎに注意しなければなりません。
WHO(世界保健機関)は、冬の室温を最低18℃以上に保つことを推奨しています。糖尿病や甲状腺機能低下症など、体温が下がりやすい持病がある人は注意が必要です。
高齢者に最適な暖房の設定温度は20~22℃、湿度は45~55%が理想だといわれています。室温を適切に管理するために、温度計や湿度計を用意して、実際の室内環境を定期的にチェックしましょう。
高齢者に最適な暖房の設定温度についてはこちら↓
高齢者に最適な暖房の設定温度は?つけっぱなしの注意点や寝るときの対応など
体を温める食事を心がける
低体温症を予防するために、タンパク質が豊富な食生活を心がけましょう。タンパク質は三大栄養素の中でも食事誘発性熱産生が高いため、十分に摂取すると体温低下を防げる可能性があります。
また、タンパク質は筋肉をつくる材料であり、日頃から摂取しておくと筋肉量が維持しやすく、筋肉による熱産生も期待できるでしょう。タンパク質は鶏肉や卵、豆腐、乳・乳製品に多いため、意識して食事に取り入れることをおすすめします。
運動習慣を身に付ける
特に寒い時期は、定期的に体を動かすようにしましょう。運動すると体の熱産生量が増えるため、低体温症のリスクを下げられる可能性があります。
ウォーキングや軽いジョギングなど、無理なく継続できる運動を日常的に行いましょう。スクワットやストレッチ、ヨガは室内でもできるため、運動習慣を付けるのに適しています。
高齢者におすすめの運動について詳しくはこちら↓
理学療法士考案!高齢者が自宅でできる運動を動画で紹介
生活習慣や環境の工夫で高齢者の低体温症を防ごう
低体温症は、内臓や脳など深部体温が35℃を下回る状態です。高齢者は寒さを感じにくく、体温調節機能が低下していたり筋肉量が低下していたりするため、低体温症になりやすいといわれています。
低体温症が進行すると命に関わる場合があり、助かったとしてもADL(日常生活動作)が低下するなど高齢者の生活に大きな影響を与える可能性があるでしょう。
低体温症は室内で発症することが多く、特に冬場は注意しなければなりません。最低でも室温は18℃以上を維持する、体を温める食事を心がける、運動習慣を付けるなど生活環境や生活習慣を工夫すると、低体温症のリスクを低下させられるでしょう。
_1.jpg)
カテゴリー|ブログ





 高齢者
高齢者
 高齢者
高齢者
 高齢者
高齢者
 高齢者
高齢者