高齢者を襲う寒暖差!季節の変わり目に体調不良から抜け出す方法は?
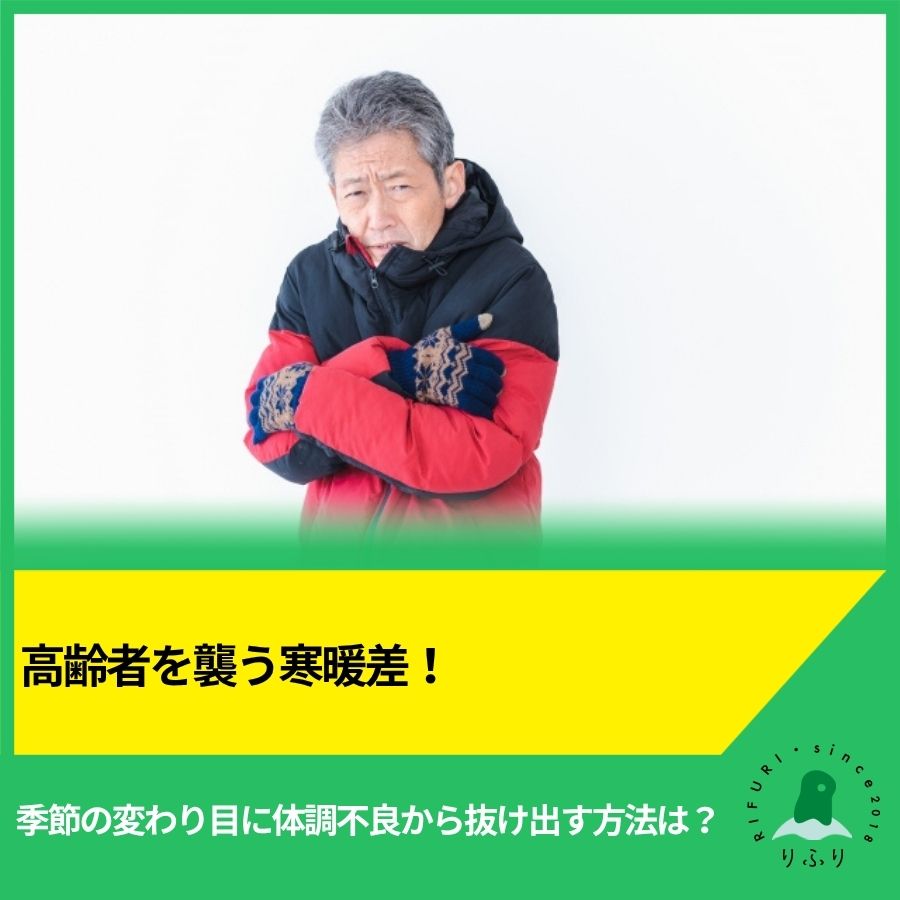
「寒暖差で高齢者に起こりやすい症状は?」
「寒暖差がある時期に高齢者が体調をくずさない方法を知りたい」
という方のために、高齢者の寒暖差による体調不良についてまとめました。
季節の変わり目になるとなんとなく体調が悪い、だるさが抜けない……そんな寒暖差による不調の原因や具体的な症状、対処法を解説します。
高齢者が寒暖差で体調不良を起こしやすい理由
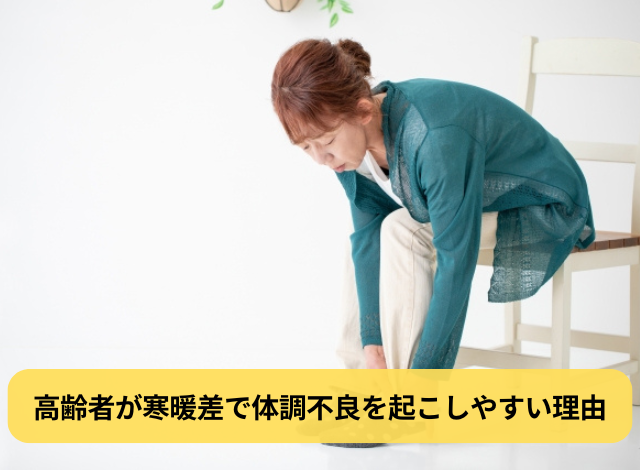
- 体温調節機能の低下
- 筋肉量の減少
- 自律神経が回復しにくい
上記のような加齢にともなう身体機能の変化で、体に負担がかかり体調を崩しやすくなります。
体温調節機能の低下
高齢になると血管の柔軟性が失われ、気温の変化に応じて血管を拡張・収縮させる機能が低下することが指摘されています。
多くの高齢者は寒いときには血管を収縮させて体温を逃がさないようにし、暑いときには血管を拡張させて熱を放出するといった調整がスムーズにいかなくなるでしょう。
また、高齢者は発汗を促す自律神経への指令が遅れたり発汗量が減少したりするため、体温を適切に下げることが困難になるという特徴があります。
結果として体が寒暖差に対応しきれず、体温調節がうまくいかなくなり疲労感や不調が蓄積していきます。
筋肉量の減少
筋肉は体内で熱を作る「熱の工場」のような役割があるため、筋肉量が減少すると熱を生み出す力が低下します。
筋肉量の減少は体温の維持や上昇を困難にし、冷えを取り除きにくい状態を作り出してしまうでしょう。
また、筋肉は血流を促進させるポンプの役割を果たしているため、筋肉量減少でポンプ作用が弱くなると血流悪化によって熱の運搬もスムーズにいかなくなります。
そのため、寒暖差を体が処理しきれずに不調を引き起こしやすくなってしまうのです。
自律神経が回復しにくい
自律神経は体温調節、血圧、心拍数など、生命維持に必要な機能を無意識に調整している神経系です。
寒暖差があると自律神経は気温に合わせて体を調整しますが、加齢によって自律神経の働きが低下し、調整後の回復にも時間がかかるようになります。
気温の変化に対して体の防御・調整システムが追いつかなくなるため、寒暖差で体調を崩しやすくなるでしょう。
高齢者は活動量の減少や外出機会の低下などから生活リズムが乱れやすく睡眠の質低下も見られる状態が多いことから、余計に自律神経の回復が遅れやすいといわれています。
高齢者が寒暖差で出やすい症状

- 寒暖差疲労
- 寒暖差アレルギー
- 寒暖差による冷え
寒暖差による不調は人によってさまざまですが、主に上記の症状がみられる傾向があります。
寒暖差疲労
寒暖差疲労とは急激な気温の変化によって自律神経が乱れ、心身にさまざまな不調が現れる状態です。
急激な気温変化に対応しようとして自律神経の調整機能が疲弊し、体温調節・心拍・消化などの調整力が落ちて倦怠感やだるさ、頭痛などが起こります。
高齢者は体温調節機能が弱く寒暖差の影響を受けやすい傾向にあるため、季節の変わり目や日夜の寒暖差が激しい季節に起こりやすいでしょう。
寒暖差アレルギー
寒暖差アレルギーは、気温差が刺激となって鼻の粘膜の血管が急激に拡張しておこるアレルギー症状です。
透明でさらさらした鼻水や連続したくしゃみ、鼻詰まりなど鼻炎のような症状が出ます。
朝起きたときや暖かい部屋から寒い場所へ移動したとき、入浴後など、温度が急変する場面で症状が出やすいのが特徴です。
高齢者は加齢により自律神経のバランスが不安定で寒暖差への適応能力が低下しているため、症状が悪化しやすいといわれています。
寒暖差による冷え
寒暖差があると体温を逃がさないように皮膚表面の血管が急激に収縮するため、血行不良を引き起こして体が冷えることがあります。
手先や足先などの末端部分は特に冷えやすく、触ると冷たく感じるでしょう。
また、寒暖差によって自律神経が疲弊すると、内臓など体の深部を適切な体温に保てなくなることがあります。
冷えを感じていなくても体の深部体温が低下している「隠れ冷え」が起こり、消化機能や免疫力といった内臓機能の低下につながるでしょう。
高齢者の寒暖差による不調を予防する方法

- 適切な環境と服装
- 朝の日光浴・夜の入浴
- 深呼吸をする
寒暖差による不調は、上記のような日常生活の中での工夫で予防・改善が期待できます。
適切な環境と服装
暖かさを保ちつつ温度差を小さくすることが、自律神経の負担を減らして体調を安定させるポイントです。
冬場の室内温度は18~22℃程度を目安に部屋ごとの温度差を小さく保つよう廊下やトイレ、脱衣所に小型のヒーターを使用しましょう。
温度差の激しい時期は重ね着で調節ができる服装を心がけ、寒い時期は首や手首、足首を温めて冷えを予防することが重要です。
外出時にはカーディガンやストールなど、調整しやすいアイテムを持ち歩きましょう。
朝の日光浴・夜の入浴
朝日には体内時計をリセットし自律神経のリズムを整える働きがあるため、朝起きたら自然光を浴びて体内時計をリセットすると体を活動モードに切り替えやすくなります。
カーテンを開けて5〜10分、できれば外に出て直接日光を浴びるのが理想的です。
また、入浴も寒暖差による不調を整える効果が期待できます。38~40℃の湯に15分前後浸かると、体リラックスモードになって自律神経が整うでしょう。
朝の日光浴と夜の入浴で体のオンオフを切り替えやすくすると、自律神経が整って寒暖差による不調を和らげられるでしょう。
深呼吸をする
深呼吸は心拍数を落ち着かせるため、血流を整える効果が期待できます。
鼻からゆっくりと肺いっぱいに息を吸い込み、口から大きくゆっくり息を吐き切る呼吸を繰り返しましょう。吸う息よりも長く息を吐くことがポイントです。
呼吸に伴って横隔膜が大きく動き、血流促進の効果が期待できます。
起床時と就寝時に5分ほど行うことが推奨されていますが、難しい場合は疲労を感じた際や気が付いたときにできる範囲で行いましょう。
危険な症状と寒暖差による不調の見分け方

- 発熱や神経症状(しびれ・麻痺)がある
- 対策をしても症状が1週間以上改善しない
- 日常生活に支障が出るほどの倦怠感や不調
寒暖差疲労だと思っていたら実は別の病気が隠れていたということもあるため、上記のようなケースは医療機関を受診しましょう。
発熱や神経症状(しびれ・麻痺)がある
寒暖差による不調は疲労感やだるさ、頭痛など自律神経の乱れからくる症状が多く、発熱や神経症状をともなわない傾向があります。
発熱がある場合は、インフルエンザや肺炎などの疾患が疑われます。また、手足のしびれや麻痺などの神経症状がある場合は、脳卒中や神経疾患の可能性があり緊急の診察が必要です。
対策をしても症状が1週間以上改善しない
適切な室温管理や服装調整、生活習慣の改善を行っても症状が1週間以上続く場合は、寒暖差以外の原因が考えられます。
高齢者は寒暖差による自律神経の乱れで体調が崩れやすい一方で、同時に感染症や心血管疾患、神経疾患などのリスクも高いことが特徴です。
自己判断で症状を軽視すると重篤な病状を見逃す恐れがあるため、1週間を目安に改善が見られない場合はかかりつけ医や内科を受診しましょう。
日常生活に支障が出るほどの倦怠感や不調
倦怠感や不調の程度が日常生活に明らかな支障をきたすレベルに達している場合は、自力で対処せず医療機関へ相談しましょう。
全身のだるさや疲労感といった軽度な症状でも、自律神経の乱れが慢性化し重大な健康問題につながるリスクがあります。
症状が我慢できないほど悪化し安静にしても改善しない場合や体力・免疫力の低下が進み、生活の質が大きく低下している場合は重大な疾患のサインかもしれません。
感染症や循環器疾患、神経疾患のリスクもあるため、症状の持続や重症化は見逃さず医療機関で検査を受けましょう。
高齢者の寒暖差対策は快適な冬を過ごすための第一歩
高齢者は、加齢により体温調節機能や自律神経の回復力の低下、筋肉量の減少で気温変化についていけず寒暖差による不調が起こります。
寒暖差が原因で出やすい症状は、疲労感やアレルギーのような症状、体の冷えです。
室温管理や服装の工夫、入浴や朝日を浴びる習慣、そして深呼吸といった日常的なケアが寒暖差に負けない体づくりにつながります。
ただし、発熱や神経症状があり1週間以上症状が改善しない、日常生活に支障が出ているといった場合は別の疾患が隠れている可能性があるため、早めの受診が大切です。
季節の変わり目を健やかに過ごすために、今日からできることを一つずつ始めてみましょう。
_1.jpg)
カテゴリー|ブログ





 高齢者
高齢者
 高齢者
高齢者
 高齢者
高齢者
 高齢者
高齢者