要介護認定を申請できる人はこんな人!条件や必要なものなど解説。本人以外の申請は?

「要介護認定を申請できるのはどんな人?」
「要介護認定を申請する際に必要な提出物や気を付けることは?」
など知りたい方のために、要介護認定を申請できる人の条件についてまとめました。
申請する際の必要書類、申請のタイミング、そして本人以外による代理申請についても詳しく解説します。
要介護認定のメリットデメリットについて詳しくはこちら↓
【要介護認定のメリット・デメリット】要介護認定で受けられる公的サービスや特徴を解説
要介護認定とは
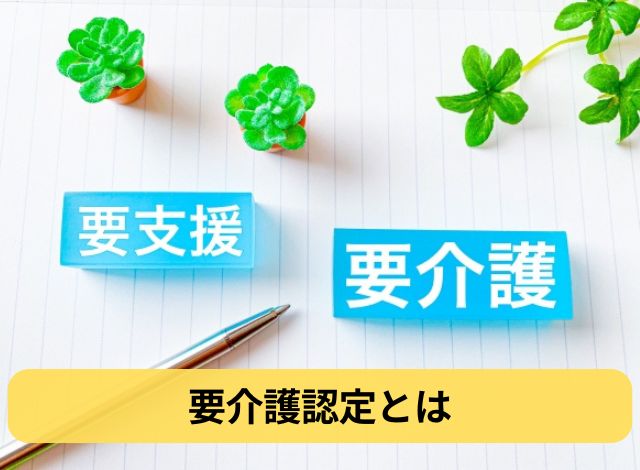
要介護認定とは、介護保険サービスを利用したい人がどれくらい介護を必要とするかを市区町村が判定する公的な審査制度です。
市区町村が実施する認定調査や医師の意見書をもとに、介護認定審査会で要支援1・2、要介護1~5の7段階、または非該当のいずれかに認定されます。
対象者の身体的・精神的な状態をもとに専門的な判断基準に沿って行われ、病気の種類や重さよりも「どの程度、日々の生活動作に介護の手間や時間がかかっているか」が重視されるでしょう。
要介護認定を受けると、訪問介護、通所介護、福祉用具レンタル、施設入所など、個人の状況に応じたさまざまな介護サービスを1~3割の自己負担で利用できます。
要介護認定について詳しくはこちら↓
要介護認定とは?区分や判定基準・申請から要介護度決定までの流れなどを解説
要介護認定を申請できる人

要介護認定を申請するには、いくつかの条件を満たしていなければなりません。申請できる人や、申請のタイミングなどを解説します。
要介護認定はどんな人が申請できる?
- 64歳9か月(65歳の誕生日の3か月前)から可能
- 65歳未満かつ16特定疾病で6か月以上の要介護・要支援状態が予想される
要介護認定を申請できるのは原則として65歳以上の第1号被保険者で、申請は65歳の誕生日の3か月前(64歳9か月)から可能です。
65歳未満でも、16種類の特定疾病により日常生活の自立が困難な状態かつ6か月以上にわたって要介護・要支援状態が続くと予想される場合は申請できます。
要介護認定の申請はいつする?
- 申請可能な条件を満たしている
- 本人が身の回りのことを自分でできなくなった
- 家族のサポートが必要な場面が多くなった
要介護認定の申請を検討すべきタイミングは、主に3つあります。
まず、申請可能な条件を満たしている場合です。65歳になる誕生日の3か月前から申請できます。
そのうえで、入浴、排泄、食事、着替え、移動などの日常生活動作(ADL)に支援が必要になったときが申請のサインです。
加えて、家族のサポートが必要な場面が多くなったときも申請を検討しましょう。
たとえば、認知機能の低下により金銭管理や服薬管理が困難になったり、買い物や掃除などの手段的日常生活動作(ADL)に介助が必要になったりした場合です。
症状が軽度でも、将来的な介護の必要性を見据えて早期に申請すると介護の負担軽減につながります。
要介護認定を受けるタイミングについて詳しくはこちら↓
要介護認定を受けるベストなタイミングは?入院中の場合やとりあえず認定される際に注意点
要介護認定の申請に必要なものは?
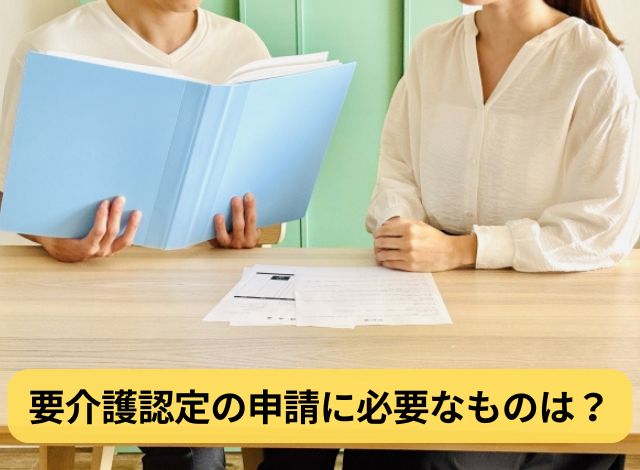
- 要介護(要支援)認定申請書
- 介護保険被保険者証
- 健康保険被保険者証(40歳~65未満の第2号被保険者)
- 個人番号(マイナンバー)
- 身分証明書(運転免許証などの顔写真付き)
- 主治医の情報が確認できるもの
要介護認定の申請には、上記の書類が必要です。
要介護(要支援)認定申請書は市区町村の窓口やホームページから入手できます。
介護保険被保険者証は必須で、紛失した場合は再交付を受けてから申請が可能です。
診察券やお薬手帳など、主治医の情報が確認できるものも用意しましょう。
必要書類は自治体によって異なるため、申請前に担当窓口に確認することをおすすめします。
要介護認定の申請は本人以外もできる?

認知症や身体機能の低下により本人による申請が困難な場合、本人以外の代理人による要介護認定の申請も認められています。
本人以外で要介護認定の申請が可能な人
- 家族
- 地域包括支援センター
- 居宅介護支援事業者
- 介護保険施設
要介護認定の申請は、本人以外だと上記が代理人となって手続きできます。申請は窓口だけではなく郵送や、一部自治体ではオンライン申請も可能です。
原則として本人の同意は必要ですが、認知症などで本人の同意が得られない場合は地域包括支援センターなど専門機関に相談すると、本人の意思を尊重しつつ適切に手続きを進めてもらえます。
本人以外が要介護認定を申請する場合の必要物
- 委任状
- 印鑑
- 代理人の身分証明書
本人以外が要介護認定を申請する場合は、申請書類に加えて主に上記の書類が必要です。
代理人が地域包括支援センターや居宅介護支援事業者などの介護関係者であれば、所属を証明する書類(社員証や在籍証明書)が必要になる場合があります。
本人が委任状に署名することが難しい場合は、本人の意思に基づいて代理人が申述書を提出するなどの対応が可能なケースもあることから、事前に自治体窓口や地域包括支援センターへ相談するとスムーズです。
必要書類は自治体によって異なる場合があるため、申請前に各自治体に確認しましょう。
要介護認定を申請する際の注意点
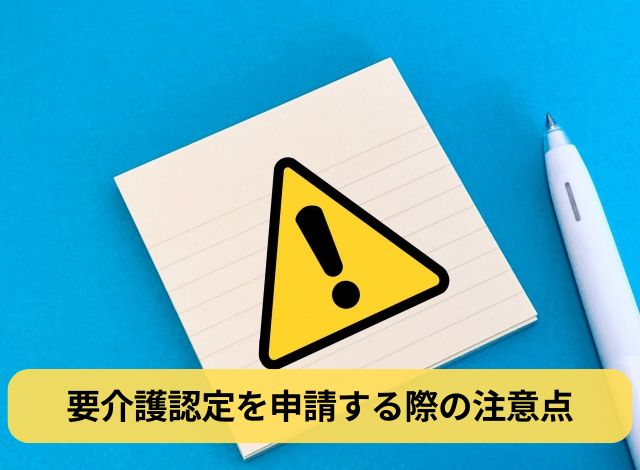
- 主治医を早めに決めておく
- 認定されない場合もある
- 認定には有効期限がある
要介護認定を申請する際には、上記に注意して申請を進めましょう。
主治医を早めに決めておく
スムーズな手続きのために、主治医(かかりつけ医)を早めに決めましょう。
要介護認定の際には市区町村が主治医に意見書を求めるため、意見書がないと認定が進みません。
主治医意見書は、申請者の心身状態や介護の必要性を医師の観点から詳しく記載するものです。
主治医がいなかったり数年前に一度受診したりしただけの医師では、状況を正確に把握できず認定がおりない事態にもなりかねません。
主治医は定期的に通院し、日常生活で本人が困っていることや身体機能の変化を相談できる関係が理想です。
地域の医療機関を定期的に受診し、信頼できるかかりつけ医を見つけておきましょう。
認定されない場合もある
要介護認定を申請しても、認定調査や医師の意見書をもとに審査した結果「日常生活に介護が必要ない」と判断された場合は、要介護・要支援のどちらも「非該当」となるでしょう。
申請要件を満たしていない場合、必要書類が整っていない場合なども却下や非該当通知となります。
申請者本人や家族が認定結果に納得できない場合、認定結果通知を受け取った日の翌日から60日以内であれば、都道府県の介護保険審査会に不服申立て(審査請求)が可能です。
要介護認定の不服申し立てについて詳しくはこちら↓
要介護認定の結果に対して不服申し立てはどこにする?メリットデメリットなども解説
認定には有効期限がある
要介護認定は有効期限が設定されており、新規申請の場合は原則6か月、更新申請の場合は12か月が期限です。
有効期間満了前に更新申請が必要で、有効期間が終わる60日前から満了日までの間に申請できます。
更新申請を忘れると認定の効力が切れてしまい、介護保険サービスが利用できなくなることもあるでしょう。
とりあえず要介護認定だけ受けることについて詳しくはこちら↓
とりあえず要介護認定だけ受けるべき?メリットデメリットや介護保険の賢い使い方
適切な要介護認定の申請で必要な介護保険サービスを受けよう
要介護認定は、65歳以上で日常生活において介護や支援が必要な状態にある方や、65歳未満でも特定疾病により介護が必要な状態が続くと予想できる方が申請できます。
本人による手続きが難しい場合は、家族や地域包括支援センターなどによる代理申請も可能です。
申請には介護保険被保険者証や身分証明書などの書類が必要で、特に主治医の意見書が認定に影響します。
認定には有効期限があるため、計画的な更新申請が欠かせません。もし認定されなかった場合も、不服申立てや再申請が可能です。
介護保険サービスを受けると本人の自立支援と家族の負担軽減が期待できるため、早めに地域包括支援センターや市区町村の担当窓口に相談して申請を検討しましょう。
介護保険は使わないと損かどうかについて詳しくはこちら↓
介護保険は使わないと損?要介護認定を受けたけど使わないとどうなる?
_1.jpg)
カテゴリー|ブログ





 高齢者
高齢者
 高齢者
高齢者
 高齢者
高齢者
 高齢者
高齢者