介護保険の住宅改修はケアマネがいないとできない?ケアマネなしの申請方法や注意点など

「ケアマネジャーがいないけど介護保険で住宅改修できる?」
「ケアマネジャーなしで住宅改修する場合に気を付けることは?」
担当ケアマネジャーがいないけど介護保険で住宅改修がしたい方へ、手順や注意点などをまとめました。
ケアマネジャーが必要になるケースにも触れているため、ぜひ参考にしてください。
介護保険で住宅改修する際にケアマネがすること

- 住宅改修についての聞き取り
- 住宅改修業者の紹介・提案・打合せ
- 申請書類の一部を作成
介護保険を利用して住宅改修する際、ケアマネジャーは上記をサポートしてくれます。
住宅改修についての聞き取り
ケアマネジャーは住宅改修を検討する際、まず高齢者本人の希望や日常生活の状況について詳しく聞き取りを行います。
病気や身体状況、将来的な変化の可能性なども考慮しながら、最適な改修プランを一緒に考えてくれるでしょう。
どんな動作に困難を感じているのか、どこで転倒リスクがあるのかなど、生活の細部まで丁寧に確認しながら、家族の状況や高齢者本人の意向も踏まえて判断します。
住宅改修業者の紹介・提案・打合せ
住宅改修業者をどう選んだらよいかわからない高齢者に、ケアマネジャーが適切な業者を紹介・提案してくれることもあります。
また、業者が現地調査する際は必要に応じて立ち会い、高齢者本人の生活や困りごとなどを確認しながら業者との打合せを円滑にしてくれるのもケアマネジャーです。
認知症などで自分の要望や悩みをうまく伝えられない高齢者にとって、ケアマネジャーは重要な代弁者となるでしょう。
申請書類の一部を作成
ケアマネジャーは、介護保険で住宅改修をする際に必要な「住宅改修が必要な理由書」を作成してくれます。
「住宅改修が必要な理由書」は、行政が改修の必要性を判断する重要な資料です。
ケアマネジャーは専門的な視点から説得力ある書類を作成し、スムーズに申請できるようサポートしてくれます。
ケアマネがいない介護保険の住宅改修

- 地域包括センターに相談
- 住宅改修施工業者の選定
- 現地調査・打合せ
- 事前申請
- 決定通知書の受け取り
- 施工・完成・施工業者への支払い
- 事後申請
- 住宅改修費の支給額決定・支給
ケアマネジャーがいなくても、介護保険を利用した住宅改修は可能です。
ケアマネジャーがいない場合は、上記の手順で住宅改修を実施しましょう。
一般的にはケアマネジャーが作成する「住宅改修が必要な理由書」は、地域包括センターに依頼すれば作成してもらえます。
介護保険を使った住宅改修の流れについて詳しくはこちら↓
介護保険で住宅改修を行う際の流れは?申請方法や申請書の記入方法について
ケアマネがいない介護保険の住宅改修で注意すべき点
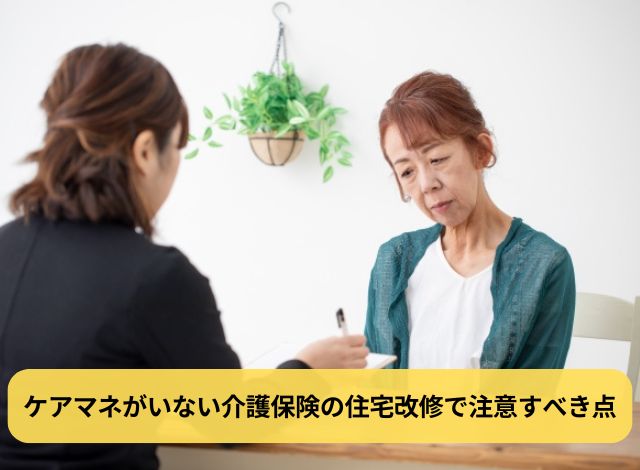
- 困っている状況や困ったエピソードを整理
- 困っている部分の動作を実際に見てもらう
- 申請前に住宅改修をしない
ケアマネジャーを介さず住宅改修の申請を行う場合に、気をつけるべき上記のポイントを解説します。
困っている状況や困ったエピソードを整理
住宅改修の申請では、なぜその改修が必要なのかを明確に説明しなければなりません。
ケアマネジャーがいない場合は、自分自身で困りごとを整理し、具体的に伝えることが必要です。
たとえば「浴室が滑って転びそうになる」「階段の上り下りがスムーズにできない」など、実際に起きた出来事を整理しておきましょう。
いつ、どこで、どんな動作をしているときに困難を感じるのかを詳しく記録し、地域包括支援センターの職員や施工業者に細かく伝える必要があります。
介護保険の住宅改修で対象外になる工事について詳しくはこちら↓
介護保険の住宅改修はどんな工事が対象?対象外のものや施工の注意点など紹介
困っている部分の動作を実際に見てもらう
言葉で説明するよりも、地域包括支援センターの職員や施工業者に実際の動きを見てもらうと問題点がより明確になります。
たとえば「トイレに座るとき手すりがほしい」というだけではなく、実際にトイレに座る動作をして、どの位置に手すりがあれば使いやすいかなど細かい確認が必要です。
家族が介助している場合は、介助の様子も見てもらうと良いでしょう。介助者の負担を軽減するための住宅改修ポイントが見えてくるかもしれません。
介護保険の住宅改修でできることについて詳しくはこちら↓
介護保険の住宅改修でできることを詳しく解説。申請方法など知っておくべきことは?
申請前に住宅改修をしない
住宅改修は、市区町村からの承認を得た後に工事を開始するようにしましょう。
事前申請なしに住宅改修を行ってしまうと、介護保険からの給付が受けられない可能性があります。
介護保険で認められる住宅改修には限度額(20万円)があることも覚えておきましょう。
ケアマネジャーがいる場合でも条件は同じですが、ケアマネジャーがいない場合は高齢者本人や家族が注意し、住宅改修のタイミングや限度額を把握しなければなりません。
介護保険でできる住宅改修の限度額について詳しくはこちら↓
介護保険の住宅改修は限度額20万円!自己負担額やリセットされる条件など解説
介護保険の住宅改修でケアマネが必要になるケース

基本的にケアマネジャーがいなくても住宅改修は可能ですが、以下のケースでは担当のケアマネジャーがいたほうが的確なサービスを受けられるでしょう。
住宅改修だけで問題が解決しない場合
住環境の改善だけでは、日常生活の困難を解決できないケースはケアマネジャーが必要になるかもしれません。
たとえば、手すりを設置しても一人での入浴が難しい場合や、段差を解消しても一人で安全に移動できない場合などです。
住宅改修と並行してほかの介護サービスを検討する必要がある状況なら、高齢者の安全な生活を確保するために、ケアマネジャーが作成する専門的視点からのケアプランが必要になるでしょう。
介護保険で手すりを設置する方法について詳しくはこちら↓
介護保険の利用で手すりの取り付け!条件や内容、申請から設置までの流れ、注意点などを解説
他の介護サービスも利用したい場合
高齢者が住宅改修以外にもデイサービスやショートステイ、訪問介護などほかの介護サービスを利用したい場合は、ケアマネジャーの選任があるとよいでしょう。
ケアマネジャーは高齢者の状態に合わせて最適なサービスの組み合わせを提案し、介護保険の範囲内で効率よくサービスを利用できるようケアプランを作成します。
複数のサービスを組み合わせて利用する場合、サービス間の調整や介護保険の限度額管理も必要となるため、ケアマネジャーの専門知識が必要になるでしょう。
介護保険の住宅改修はケアマネなしで可※必要になるケースも
介護保険の住宅改修は、ケアマネジャーがいなくても地域包括支援センターに相談すれば可能です。
その際は、住宅改修が必要な状況を整理し、工事開始のタイミングなどに注意しましょう。
住宅改修だけでは解決しない課題がある場合や、ほかの介護サービスも利用したい場合は、ケアマネジャーを選任すれば総合的な視点から継続的なサポートを受けられるでしょう。
住み慣れた自宅で安全な暮らしを続けるためには、住環境の整備が不可欠です。必要に応じてケアマネジャーのサポートを取り入れながら、介護保険の住宅改修制度を上手に活用し、住環境を整えましょう。
_1.jpg)
カテゴリー|ブログ





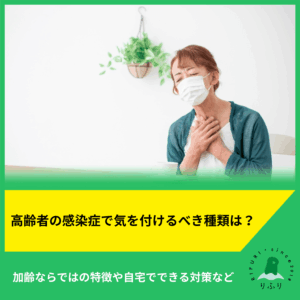 高齢者
高齢者
 高齢者
高齢者
 高齢者
高齢者
 高齢者
高齢者