介護保険で住宅改修を行う際の流れは?申請方法や申請書の記入方法について
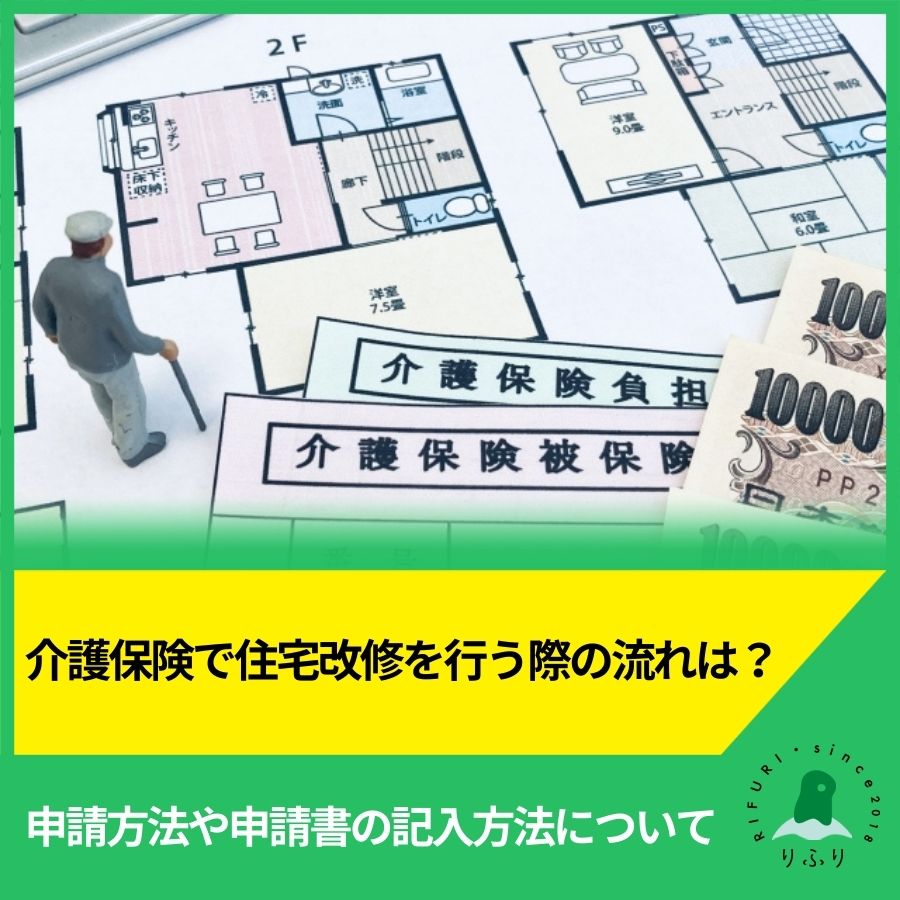
「介護保険で住宅改修するときの手順は?」
「介護保険で住宅改修する際の申請方法が知りたい」
など、介護保険を利用して住宅改修を行う際の流れについて知りたい方のために、申請方法などをまとめました。
制度を利用すれば、手すりの設置や段差解消など工事費用の一部が介護保険から給付されるため、経済的な負担を抑えながら住環境を整えられるでしょう。
申請前の準備から工事後の手続きまでわかりやすく解説します。
介護保険で取り付ける手すりについて詳しくはこちら↓
介護保険の利用で手すりの取り付け!条件や内容、申請から設置までの流れ、注意点などを解説
介護保険の住宅改修について

介護保険の住宅改修は、要介護または要支援と認定された方へ向けて、自宅での生活を支援するために行う改修工事です。日常生活動作(ADL)の自立を促進し、本人と介護者の負担軽減を目的としています。
利用できるのは、要支援1~2または要介護1~5と認定された方です。
対象となる工事には、手すりの設置、段差の解消、滑りにくい床材への変更、引き戸への取り替え、洋式トイレへの変更などが含まれています。
介護保険を利用した住宅改修でできることについて詳しくはこちら↓
介護保険の住宅改修でできることを詳しく解説。申請方法など知っておくべきことは?
介護保険の住宅改修を行う際の流れ

- 要介護・要支援認定
- ケアマネジャーへ相談
- 住宅改修事業者選定
- 現地調査・打合せ・住宅改修プラン作成
- 見積書と工事図面の確認
- 事前申請
- 決定通知書の受け取り
- 施工・完成・施工業者への支払い
- 事後申請
- 住宅改修費の支給額決定・支給
介護保険の住宅改修は、主に上記の流れで実施します。
要介護・要支援認定
要介護・要支援認定を受けていない場合は、住宅改修費の支給対象とはならないため、まずは認定申請を行いましょう。
申請は市区町村の介護保険窓口で申請し、申請後は調査員による訪問調査と主治医の意見書をもとに審査が行われます。
認定結果は「非該当」「要支援1・2」「要介護1~5」のいずれかで、住宅改修の対象は要支援・要介護1以上の認定を受けた方です。
認定の有効期間は基本12か月であるため、有効期間内であれば住宅改修を申請できます。期間が近々切れる場合は更新申請も並行して行うと安心でしょう。
要介護認定についてはこちら↓
【要介護認定のメリット・デメリット】要介護認定で受けられる公的サービスや特徴を解説
ケアマネジャーへ相談
要介護度が認定されたあと、ケアマネジャーへ住宅改修が必要である旨を相談しましょう。
「トイレでの立ち座りが辛い」「浴室で転びそうで不安」など、現在の住環境で困っている点や不便に感じる点を具体的に伝えると、スムーズな進行が可能です。
ケアマネジャーは相談内容をもとにどんな住宅改修が必要か提案してくれるでしょう。
ケアマネジャーがいない場合の住宅改修についてはこちら↓
介護保険の住宅改修はケアマネがいないとできない?ケアマネなしの申請方法や注意点など
住宅改修事業者選定
ケアマネジャーと相談した結果、住宅改修が必要であるという結論に至ったら住宅改修業者を選定しましょう。
業者選定のポイントは、介護保険の住宅改修制度に精通しているか、高齢者向けの改修工事で高い実績があるか、アフターフォローはどうかなどです。
ケアマネジャーが適切な業者を紹介してくれる場合もあります。
品質や工事の詳細内容、保証内容などもふまえて複数複数社で見積もりをとり、比較検討しましょう。
現地調査・打合せ・住宅改修プラン作成
住宅改修業者が決まったら、実際に住宅を訪問してもらい、ケアマネジャーも交えて現地調査と詳細な打合せを行います。
打合せの際、日常生活での困りごとや不安な点などを詳細に伝えるだけではなく、実際の動作を目視してもらうことが大切です。
改修が必要な箇所の状態や寸法、必要な工事などを確認し、具体的な住宅改修プランを作成してもらいましょう。
介護保険を利用した住宅改修の対象工事について詳しくはこちら↓
介護保険の住宅改修はどんな工事が対象?対象外のものや施工の注意点など紹介
見積書と工事図面の確認
住宅改修プランが作成されたら、見積書と工事図面が住宅改修業者から提出されます。
費用や工事内容が希望に沿ったものか、困りごとを解決するものかなどを確認しましょう。
不明点などは業者に説明を受け、明確にしておくことが重要です。
事前申請
- 住宅改修費支給申請書【事前】
- 住宅改修が必要な理由書
- 工事費見積書
- 住宅改修前の状態がわかるもの
- 住宅改修施工計画書
- 承諾書
見積書と工事図面の内容に納得したら、上記の書類を用意して事前申請を行います。
申請書類は市区町村によって若干異なるため、ケアマネジャーに依頼するとスムーズにそろえることが可能です。
「住宅改修が必要な理由書」は、一般的にケアマネジャーが作成してくれます。
「住宅改修前の状態がわかるもの」として、改修予定箇所の写真や図面を用意しましょう。玄関、廊下、浴室、トイレなど、改修する場所をさまざまな角度から撮影しておきましょう。
申請は工事着工前に行わなければなりません。申請前に工事を始めてしまうと、介護保険が使えなくなる可能性があるため注意が必要です。
決定通知書の受け取り
事前申請書類の提出後に市区町村で審査が行われ、承認されると「住宅改修費支給決定通知書」が自宅に郵送されてきます。通知書は住宅改修工事を始めるための正式な許可証となるため、大切に保管しておきましょう。
審査から決定通知書が発行されるまでの期間は自治体によって異なり、1週間から10日程度かかることがほとんどです。
決定通知書を受け取った後に初めて工事を開始できるというルールであるため、通知書を受け取る前に工事を始めないようにしてください。
施工・完成・施工業者への支払い
決定通知書が届いたら住宅改修工事が施工されます。
工事が完了したら、住宅改修業者から説明を受けながら改修箇所をすべて確認しましょう。住宅改修プランに沿った内容かどうか、使い方、使い勝手などをチェックし、問題なければ、住宅改修業者から「工事完了証明書」と「領収書」を受け取って支払い手続きです。
事後申請
- 住宅改修費支給申請書【事後】
- 住宅改修にかかった費用の領収書
- 工事費内訳書
- 住宅改修後の状態を確認できる書類
工事が完了したら上記の書類を用意し、住宅改修費の支給を受けるための事後申請を行います。
必要書類は市区町村によって若干異なる場合があるため、事前に担当窓口で確認しておきましょう。
「住宅改修後の状態を確認できる書類」には改修箇所の工事完了後の写真を添付し、ビフォーアフターを比較しやすくすると審査がスムーズに進みます。
住宅改修費の支給額決定・支給
事後申請の書類を提出すると、市区町村で最終的な審査が行われ、問題がなければ「住宅改修費支給額決定通知書」が発行されます。
住宅改修費支給額決定通知書には実際に支給される金額が記載されているため、申請した金額と一致しているかを確認しましょう。
償還払いもしくは受領委任払いにて支払いが済むと、住宅改修における一連の流れは完了です。給付金が指定の口座に振り込まれるのを待ちましょう。
介護保険を利用した住宅改修の限度額について詳しくはこちら↓
介護保険の住宅改修は限度額20万円!自己負担額やリセットされる条件など解説
介護保険の住宅改修申請における償還払いと受領委任払い
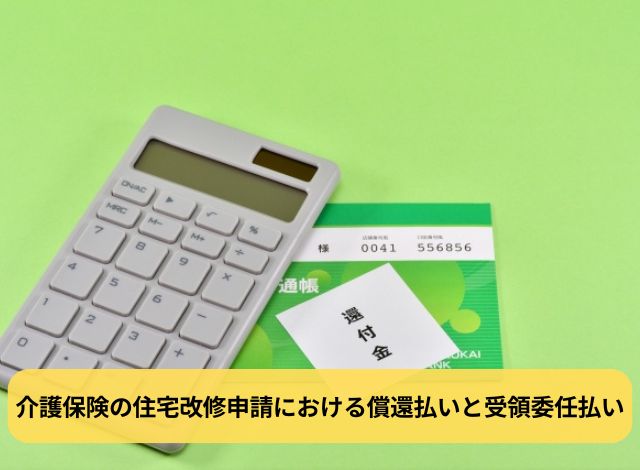
介護保険の住宅改修には「償還払い」や「受領委任払い」という支払い方法があります。
それぞれについて詳しくみていきましょう。また、どちらを選べるかは市区町村や住宅改修業者などによって異なります。
償還払いとは?
償還払いは、利用者がまず工事業者に住宅改修費用の全額を支払い、事後申請したあと保険給付分を受け取る方法です。
一時的に全額を立て替える必要があるため、計画的に実施しないと経済的負担が大きくなる可能性があります。
受領委任払いとは?
受領委任払いは、利用者が工事業者に自己負担分のみを支払い、残りは事後申請後に市区町村から直接住宅改修業者に支払われる仕組みです。
利用者の一時的な経済的負担が少なくて済みますが、住宅改修業者によって対応していない場合があるため、注意しましょう。
介護保険の住宅改修で安心な暮らしを維持しましょう
要支援1・2または要介護1~5と認定された方は、介護保険を利用して住宅改修が可能です。
要介護・要支援認定の取得から始まり、ケアマネジャーへの相談、住宅改修事業者の選定、現地調査と改修プランの作成、見積書と工事図面の確認、事前申請、決定通知書の受け取り、事後申請と、漏れなく手続きすれば改修費用の一部が給付されます。
支給方法には全額を一時的に立て替える「償還払い」と、自己負担分のみを支払う「受領委任払い」があることを知っておきましょう。
高齢者の安全な暮らしを確保するために、ケアマネジャーに相談しながら介護保険の住宅改修を活用しましょう。
_1.jpg)
カテゴリー|ブログ





 リクルート
リクルート
 高齢者
高齢者
 高齢者
高齢者
 高齢者
高齢者