介護保険の住宅改修でできることを詳しく解説。申請方法など知っておくべきことは?
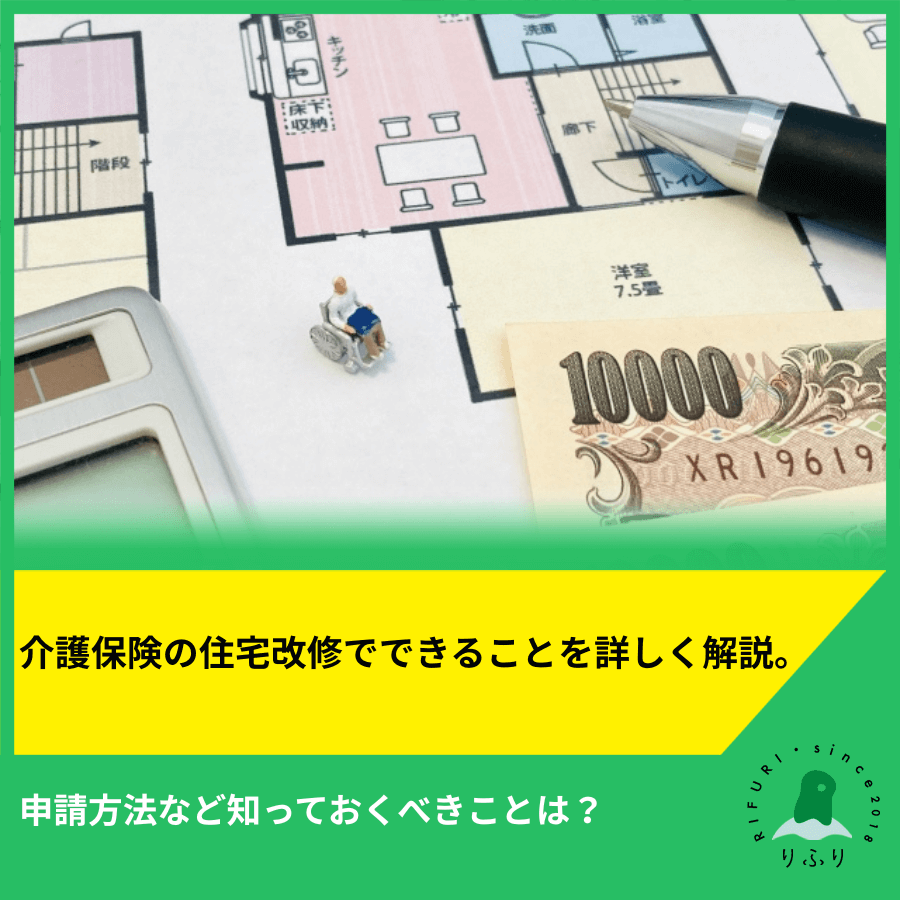
「介護保険の住宅改修ではどんなことができる?」
「介護保険を使って住宅改修する場合、どうやって申請するのかな」
など調べている方のために、情報をまとめました。
制度を利用すれば介護保険制度から補助金が支給されるため、経済的な負担を抑えつつ、自宅を快適な環境に改修できるでしょう。
この記事では、介護保険で住宅改修する際にできることや申請方法、具体的な住宅改修例などを解説しています。ぜひ参考にしてください。
介護保険の住宅改修って?

介護保険の住宅改修とは、要介護認定を受けた要介護者が自宅で安全に暮らせるように、住居の改修にかかる費用の一部が介護保険制度から支給されるサービスです。
対象者や目的、支給限度額について詳しく見ていきましょう。
対象者
対象となるのは、要支援1・2あるいは要介護1~5の要介護認定を受けていて、介護保険被保険者証に記載された住所に住んでいる方です。入院していたり介護施設などで生活していたりする場合は、支給対象にはなりません。
ただし、今後改修される予定の住宅に戻ることが決定していると、支給対象になるケースがあります。
目的
介護保険の住宅改修は、要介護者が自宅で安全に自立生活を送れるようにすることが第一の目的です。加齢や障害によって身体機能が低下した場合でも、自宅の環境を整えれば、生活の質を維持・向上させられるでしょう。
また、介護者の負担軽減も目的の一つです。改修によって介護しやすい動線になったり要介護者のできることが増えたりすると、介護者の身体的な負担を減らせるでしょう。介護がスムーズに行えることで、精神的な負担も軽減する可能性があります。
支給限度額
介護保険による住宅改修には支給限度額があり、最大20万円までと定められています。20万円までなら、所得に応じて1~3割負担で改修工事が可能です。
20万円を超過した分は全額自己負担で、20万円以内であっても1~3割は自己負担分が発生することに注意しましょう。また、合計20万円に達するまで複数回に住宅改修を分けることもできます。
1回目はスロープの設置、2回目は床材の変更など、要介護者の状況に合わせて計画的に利用しましょう。
介護保険の住宅改修における支給限度額について詳しくはこちら↓
介護保険の住宅改修は限度額20万円!自己負担額やリセットされる条件など解説
介護保険の住宅改修でできること

- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- その他対象の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
介護保険の住宅改修で対象となるのは、上記6つの工事です。
転倒予防や安全な移動のサポートなど、要介護者の自立生活を支える工事やその工事に付随して必要な工事が対象です。見映えの向上や老朽化による取り替え、利便性を高めるための工事は対象になりません。
たとえば、手すりを取り付ける際に壁の補強が必要な場合は、手すりの取り付けと壁の補強、その際に生じたクロスの一部貼り替えなどが対象です。
装飾性が高い手すりの設置やクロス全体の変更などは対象外となり、そのほか身体機能の補助や安全性が目的ではない工事は承認されないでしょう。
なお、段差解消機や昇降機など動力を使った設備は対象外です。段差解消機や昇降機を設置しても段差そのものは残されたままであり、段差解消が目的ではないと判断されるためです。
また、和式トイレ用腰掛便座などは福祉用具のレンタルや購入をサポートする他の介護保険サービスが適用されるため、対象になりません。
介護保険の住宅改修で対象外になる工事について詳しくはこちら↓
介護保険の住宅改修はどんな工事が対象?対象外のものや施工の注意点など紹介
介護保険で住宅改修する際の流れ
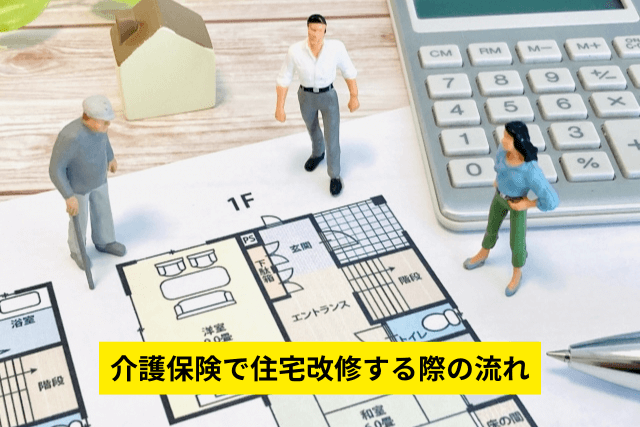
- 要介護・要支援認定
- ケアマネジャーへ相談
- 住宅改修事業者選定
- 現地調査・打合せ・住宅改修プラン作成
- 見積書と工事図面の確認
- 事前申請
- 決定通知書の受け取り
- 施工・完成・施工業者への支払い
- 事後申請
- 住宅改修費の支給額決定・支給
介護保険で住宅改修する場合、上記の流れで実施します。
介護保険の住宅改修は介護認定を受けていることが前提であるため、まずは要支援・要介護認定を受けましょう。
次に、ケアマネジャーと相談して、必要な住宅改修の内容を検討します。
改修の内容が決定したら、住宅改修事業者を選定しましょう。ケアマネジャーが紹介してくれる場合もあります。
業者の決定後、自宅で現地調査と詳細な打ち合わせを行い、具体的な住宅改修プランを作成してもらいましょう。
住宅改修プランが作成されると、見積書と工事図面が住宅改修業者から提出されます。内容を確認し、問題がなければ事前申請を行いましょう。
事前申請書類を提出して市区町村に承認されると、自宅に「住宅改修費支給決定通知書」が届きます。その後、着工するため、工事完了後に「工事完了証明書」と「領収書」を受け取り、支払いを済ませましょう。
工事完了後は、住宅改修改修費の支給を受けるために事後申請を行います。各自治体が定める必要書類を提出し、最終的な審査に通れば「住宅改修費支給額決定通知所」が発行されるため、申請した金額と一致しているかを確認しましょう。
介護保険を利用した住宅改修の流れについて詳しくはこちら↓
介護保険で住宅改修を行う際の流れは?申請方法や申請書の記入方法について
介護保険の住宅改修例

介護保険における住宅改修で具体的にどのような工事が行えるのか、玄関・トイレ・浴室の3例について解説します。
玄関
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑りにくい床材に変更
- 足元灯の設置(×)
玄関で上記の工事を行った場合、手すりの取り付けや段差の解消、滑りにくい床材への変更が介護保険が適用される住宅改修です。
手すりの取り付けは玄関のなかだけではなく、玄関から道路までの手すりも設置することができます。
足元灯の設置は介護保険の対象外となる工事です。夜間の通行はしやすくなりますが、天井照明があれば問題ないと考えられているからでしょう。
介護保険を利用した手すりの取り付けについて詳しくはこちら↓
介護保険の利用で手すりの取り付け!条件や内容、申請から設置までの流れ、注意点などを解説
トイレ
- 手すりの取り付け
- 和式便器から洋式便器への変更
- 開き戸から引き戸への取替え
- 暖房機の取付(×)
- 片手で切りやすいペーパーホルダー設置(×)
トイレで上記の住宅改修をした場合、手すりの取り付けや洋式便器への変更、開き戸から引き戸への取替えに介護保険が適用されます。
暖房機の取り付けはヒートショック対策に有効ですが、他の方法でも対処できるため、住宅改修の対象外です。また、片手で切りやすいペーパーホルダーも利便性を高めるものと判断されることから、介護保険を使っての改修はできません。
浴室
- 段差解消に伴うユニットバスの取替え
- 滑りにくい床材に変更
- 手すりの取り付け
- 洗面器棚設置(×)
- 換気扇の取替え(×)
浴室や浴槽の出入りをスムーズに行えるように、ユニットバスへの取替え工事や滑りにくい床材への変更工事が可能です。転倒防止や立ち上がり補助のために手すりを取り付ける工事も介護保険で行えます。
洗面器棚の設置や換気扇の取替え工事は利便性の向上や老朽化に伴う工事と判断され、介護保険を使うことができません。
介護保険で住宅改修するメリット

- 自立生活の継続と在宅介護の負担軽減
- 介護リフォーム費用の節約
- 身体機能の維持
介護保険で住宅改修をすると、上記のようなメリットが得られます。一つずつ、詳しく解説します。
自立生活の継続と在宅介護の負担軽減
手すりの設置や段差の解消、浴室やトイレの改修などによって日常生活の動作がスムーズに行えるようになると、要介護者が自立した生活を継続しやすくなります。
ひとりでできることが多ければ生活のモチベーションも向上し、ライフワークにもいい影響を与えるでしょう。
また、介護しやすい住環境を整えれば、家族などの介護者も大きな負担を感じることなく在宅介護が可能です。
介護リフォーム費用の節約
介護保険を利用した住宅改修では、一定の条件を満たす工事に対して補助金が支給されることから、所得に応じて1~3割の自己負担のみで工事が可能です。
限度額内の改修工事であれば、介護リフォーム費用を大きく節約できるでしょう。
介護保険を活用して予算が余れば、対象外とされている工事を自己負担で実施してより便利な生活空間を作ることもできます。
身体機能の維持
住宅改修によって住環境が改善されると、要介護者が自力で移動や立ち座りなどがしやすくなり、安全に動くことが可能です。
自分でできる動作が増える点や寝たきりの原因になりやすい転倒を防げる点から、住宅改修は身体機能の維持に役立つといえます。
また、自立生活は介護者任せではなく、自分で自分の生活をコントロールする必要が出てくるため、認知機能の維持にもつながるでしょう。
介護保険で住宅改修するデメリット
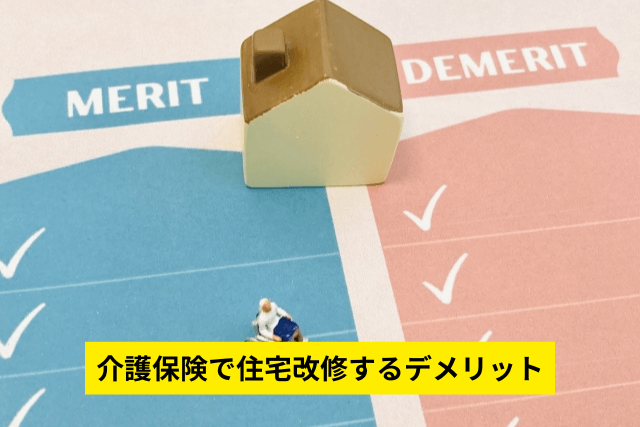
- 手続きが複雑で時間がかかる
- 支給額や工事内容が限られている
介護保険の住宅改修は、メリットだけではありません。手続きの煩雑さや限度額が設定されている点などはデメリットになり得るため、事前にしっかりと把握しておきましょう。
手続きが複雑で時間がかかる
改修前にケアマネジャーや住宅改修業者との打ち合わせが必要であったり、市区町村に事前申請を行う必要があったり、手続きが煩雑かつ時間がかかる点はデメリットです。
要介護認定を受けていない場合は、まず要介護認定を受けることから始めなければならず、非常に多くの時間を要します。
たとえば、医療機関から退院直後に自宅の改修が必要になった場合などは注意が必要です。複雑な手続きのせいですぐに住宅改修ができず、一定期間は負担が大きい生活となる可能性があります。
また、事前申請が承認されていない状態で着工してしまうと、支給対象外になるリスクがあるため、急いでいても慎重に手続きを進めなければなりません。
必要なときに住宅改修が行えるように、地域包括支援センターや担当ケアマネジャーと密に連携しておくことが大切です。
支給額や工事内容が限られている
介護保険を使った住宅改修の支給限度額は最大20万円と決められています。そのため、計画的に住宅改修を進めなければなりません。
また、支給対象となる工事は「手すりの取り付け」や「段差の解消」などに限られています。
支給額や改修工事の内容が限定されているため、要介護者や介護者の希望が満たされない可能性もあるでしょう。
介護保険の住宅改修で知っておくべきこと
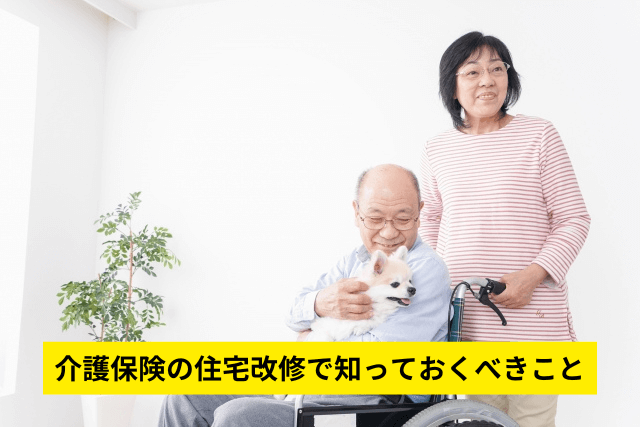
- ケアマネなしでも介護保険で住宅改修できることがある
- 自分で工事した場合は材料費が対象となる
- 事前申請して許可が出てから工事開始
介護保険を使った住宅改修は、ケアマネジャーがいなくても可能であったり自分で工事した場合は材料費が対象になったりします。
また、事前申請に許可がおりてから着工する流れは、絶対に守らなければなりません。住宅改修について知っておくと有益な情報を3つ、詳しく解説します。
ケアマネなしでも介護保険で住宅改修できることがある
介護保険の住宅改修は、ケアマネジャーがいなくても手続き可能です。担当のケアマネジャーがいない場合は、地域包括支援センターに相談すれば対応してもらえます。
介護保険で住宅改修する際に必要となる「住宅改修が必要な理由書」については、地域包括支援センターが作成してくれるため、ケアマネジャーがいなくても問題ありません。
ケアマネジャーなしで住宅改修を進めることになる場合、日常生活の困りごとを具体的に地域包括支援センターの相談員に伝え、実際の動作を見てもらうことが大切です。実際に見てもらうことで、要介護者・介護者が抱える問題点が明確化され、適切な改修工事ができる可能性を高められるでしょう。
ケアマネジャーなしで住宅改修する場合について詳しくはこちら↓
介護保険の住宅改修はケアマネがいないとできない?ケアマネなしの申請方法や注意点など
自分で工事した場合は材料費が対象となる
自分で工事した場合は、材料費のみが対象となります。介護保険の住宅改修は限度額が20万円と限られているため、自分で工事すると節約になるでしょう。
しかし、見積書や工事図面、工事費内訳書などを自分で用意しなければならなず、手続きが難航する可能性が高くなります。正しい手順で工事を進められるよう、事前に地域包括支援センターやケアマネジャーとよく相談することが重要です。
事前申請して許可が出てから工事開始
市区町村に事前申請して許可が出てから工事を開始しなければ、介護保険からの給付が受けられない可能性があります。給付が受けられない場合は全額自己負担しなければならず、経済的な負担が大きくなるでしょう。
特に担当ケアマネジャーがいない場合は、要介護者や家族が改修工事のタイミングを間違わないように注意しなければなりません。
介護保険の住宅改修は、要介護者の自立した生活を維持するための工事が可能
介護保険の住宅改修では、要介護者が自宅で自立した生活を送れるようにするために、手すりの取り付けや段差の解消などの5つの工事と、それらに伴って必要な工事が行えます。
たとえば、浴室での改修工事では、浴室や浴槽の出入りを安全に行えるように、ユニットバスへの取替え工事や滑りにくい床材への変更工事が可能です。しかし、洗面器棚の設置や換気扇の取替え工事は、利便性の向上や老朽化に伴う工事となるため、住宅改修の対象外と判断されます。
また、工事前に市区町村に事前申請しなければ、介護保険からの給付が受けられません。地域包括支援センターやケアマネジャーと相談しながら正しい手順で手続きを行い、自宅の住環境を整えましょう。
_1.jpg)
カテゴリー|ブログ





 高齢者
高齢者
 高齢者
高齢者
 高齢者
高齢者
 高齢者
高齢者