介護保険の住宅改修は限度額20万円!自己負担額やリセットされる条件など解説
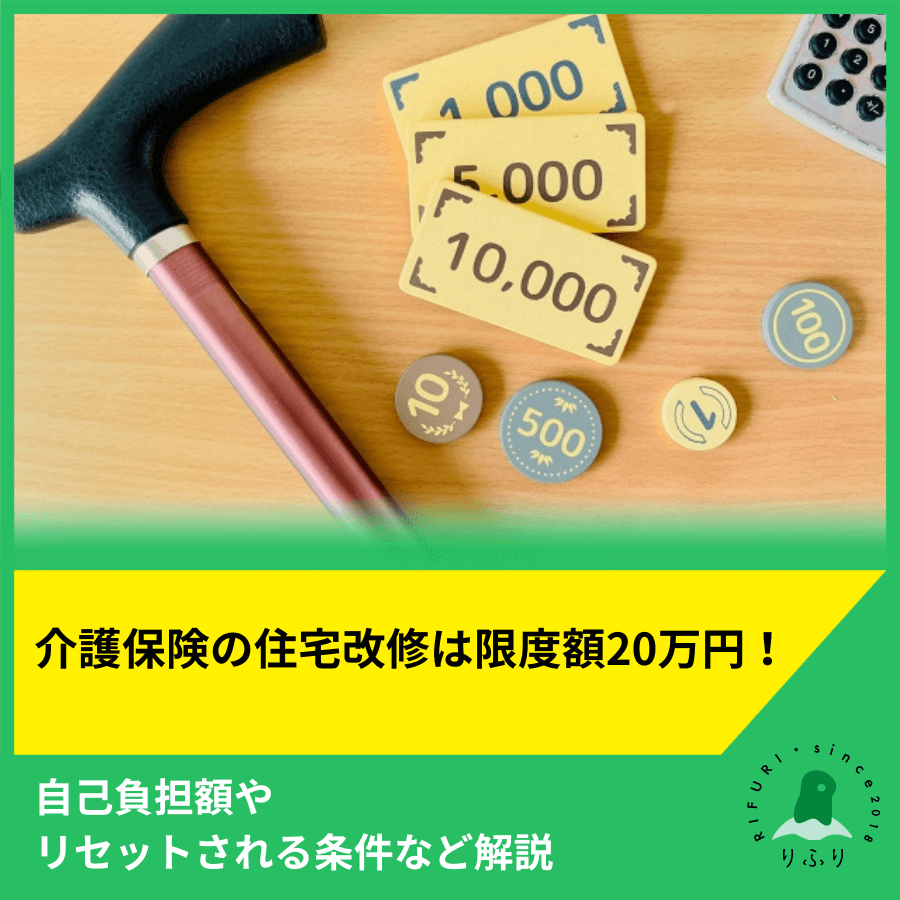
「介護保険でできる介護リフォームの限度額について知りたい」
「介護保険の住宅改修で限度額20万円がリセットされることはある?」
など調べている方のために、情報をまとめました。
介護保険の住宅改修は限度額20万円と決められており、使い方などのルールが設けられています。
この記事では、介護保険でできる住宅改修の限度額や自己負担額の例、リセットされる条件や注意点などを解説しているため、ぜひ参考にしてください。
介護保険を利用した住宅改修の流れについて詳しくはこちら↓
介護保険で住宅改修を行う際の流れは?申請方法や申請書の記入方法について
介護保険の住宅改修とは?
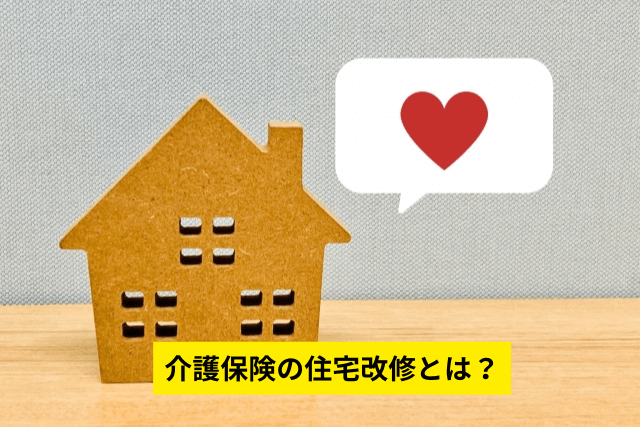
介護保険の住宅改修とは、要介護認定を受けた要介護者が自宅で安全かつ快適に暮らせるようにするため、一定の条件を満たす住宅改修工事に対して介護保険制度から補助金が支給されるサービスです。
対象となるのは、手すり、段差の解消、床・通路の材料変更、扉付け替え、便器交換に加え、それら5つの工事に付帯する工事、の6つの工事に限られます。やりたい工事を何でも行えるわけではありません。
たとえば、介護が必要で車椅子を使う生活になる場合、スロープや手すりの導入などで住みやすい住環境となるでしょう。
まずは、自宅の改修が必要かどうか担当のケアマネジャーに相談することから始めましょう。必要がある場合は、申請書類を役所に提出して、申請が承認されたら工事が実施される流れとなります。
介護保険の住宅改修で対象外となる工事について詳しくはこちら↓
介護保険の住宅改修はどんな工事が対象?対象外のものや施工の注意点など紹介
介護保険の住宅改修における限度額や自己負担額

介護保険の住宅改修は、限度額が設けられており、限度額を超える分は自己負担しなければなりません。限度額や限度額までの使い方、自己負担額の例を交えて分かりやすく解説します。
介護保険の住宅改修でできることについて詳しくはこちら↓
介護保険の住宅改修でできることを詳しく解説。申請方法など知っておくべきことは?
限度額は20万円
介護保険を利用して住宅改修を行う場合、支給限度額は最大20万円までと決まっています。20万円までなら、所得に応じて1~3割負担で改修工事が可能です。20万円を上回る分は、全額自己負担となります。
上限なく介護保険を使って住宅改修できるわけではなく、限度額内であっても自己負担額がゼロというわけでもありません。
また、20万円までなら複数回に分けて住宅改修を行うこともできます。たとえば、1回目は手すりを設置して2回目は階段をスロープにするなど、身体状況などに合わせて複数回の工事が可能です。
なお、工事にかかった金額は一度すべて工事会社に全額支払い、後から介護保険分が払い戻しされる仕組みになっています。一度はまとまった資金が必要になることを、念頭に置いておきましょう。
自己負担額の例
| 工事内容 | 費用 | 自己負担額 (1割負担の場合) | 残額 |
|---|---|---|---|
| 手すりの取付 | 5万円 | 5,000円 | 15万円 |
| 段差の解消 | 10万円 | 10,000円 | 5万円 |
| 便器の取替 | 10万円 | 5,000円+5万円※ | -5万円 |
1割負担の場合で必要な自己負担額の例を表にしました。
たとえば、5万円かかる手すりの取付工事を行った場合、自己負担額は1割相当の5,000円です。支給限度額である20万から工事費用の5万円を差し引いた15万円が、介護保険の対象となる残高となります。
続いて段差を解消する10万円の工事を行った場合、自己負担額は10,000円、残高は5万円です。
次に、便器の取替工事に10万円使った場合、10万円のうち残高分の5万円は介護保険の対象となり、1割相当の5,000円が自己負担となります。残りの5万円は限度額の20万円を超えた分であるため、そのまま負担しなければなりません。
介護保険を利用した手すりの取り付けについて詳しくはこちら↓
介護保険の利用で手すりの取り付け!条件や内容、申請から設置までの流れ、注意点などを解説
介護保険の住宅改修│限度額がリセットされる条件

- 要介護度が3段階上がった
- 転居して住民票を移した
介護保険の住宅改修は、使い切ってしまうと基本的に復活しません。
しかし、条件によっては限度額がリセットされ、再び介護保険を使っての住宅改修が可能です。限度額がリセットされる、2つの条件についてご紹介します。
要介護度が3段階上がった
初回の住宅改修から、要介護度が3段階上がったら限度額がリセットされます。ただし、要支援2と要介護1は、同じ区分として考えられるため、要支援1から3段階上がった状態は要介護3以上です。
また、要介護3・4・5の場合、3段階以上上の介護度がないことから、要介護度が上がる条件でのリセットはありません。
転居して住民票を移した
転居して住民票を移した場合、新しい住居で改修が必要になったときは、再度20万円の限度額が復活します。
ただし、住宅改修後に転居して転居先でも住宅改修をした後、転居前の住居に戻った場合、すでに住宅改修済みの住居への移動であるため、住民票の移動があってもリセットの対象にはなりません。
また、住民票を移す必要がない別荘なども、リセットの対象外です。
介護保険の住宅改修│限度額がリセットされる際の注意点
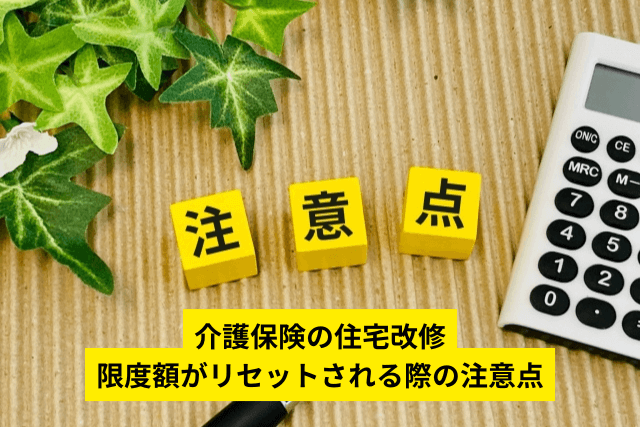
- 残高があっても20万円に上乗せされない
- 住宅改修後に要介護度が下がったあと3段階上がってもリセットされない
- 2回目の3段階リセットは適用されない
介護保険の住宅改修を賢く活用するために、事前に注意点を把握しておきましょう。リセットされる際の注意点を3つ解説します。
残高があっても20万円に上乗せされない
支給額に残高がある状態で限度額がリセットされる場合、残高は新しく支給される20万円には合算されません。
たとえば、要支援1のときに1回目の住宅改修を行い、15万円かかったとします。残高は、5万円です。
介護認定の更新で要介護4になった場合、3段階リセットが適用されて再び20万円が支給されますが、残高の5万円は上乗せされません。どれだけ残高があっても、リセット後の支給限度額は20万円です。
住宅改修後に要介護度が下がったあと3段階上がってもリセットされない
一度住宅改修をした後に要介護度が下がったあと、再び要介護度が3段階上がってもリセットされません。
例を挙げると、初めて住宅改修をしたときは要支援2で、その後、介護状態が改善して介護認定は非該当になったとします。再び介護状態になり、要介護2の認定を受けたとすると、3段階上がった状態です。
しかし、基準は1回目の住宅改修を行った時点での介護度で、そこから数えて要介護度が3段階以上あがっていなければリセットされません。
2回目の3段階リセットは適用されない
3段階リセットの適用は原則1人につき1回までとされており、2回目以降は適用されません。
要支援1の状態で1回目の住宅改修を限度額まで利用した後、要介護度が3段階上がって要介護3になると、住宅改修の限度額がリセットされます。
その後、要介護2まで要介護度が下がり、再び要介護度が3段階上がって要介護5になったとしても、3段階リセットは2回目となるため適用されません。
対象となる条件や例外を理解して、賢く制度を活用しよう
介護保険の住宅改修とは、高齢者や要介護者が自宅で安全かつ快適に過ごすために、一定の条件を満たす住宅改修工事に対して介護保険制度から補助金が支給される制度です。
限度額は20万円と決められていますが、要介護度が3段階上がったり転居したりと、条件を満たすと限度額がリセットされて、再び20万円まで介護保険を利用した住宅改修が可能となります。
ただし、1回目の工事をして20万円を使い切らず、残高があったとしても次に20万円支給されるときには上乗せされないなどいくつかルールがあるため、注意が必要です。
限度額について正しい知識を持ち、制度を最大限に活用して自宅を快適な環境に改修しましょう。
介護保険の住宅改修でケアマネがいないときの対処法について詳しくはこちら↓
介護保険の住宅改修はケアマネがいないとできない?ケアマネなしの申請方法や注意点など
_1.jpg)
カテゴリー|ブログ





 リクルート
リクルート
 高齢者
高齢者
 高齢者
高齢者
 高齢者
高齢者